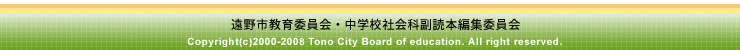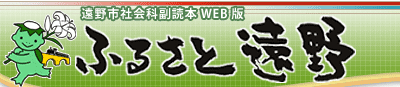 |
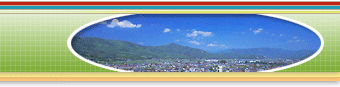 |
||
| 1.原始時代の遠野 | |
| ・ | 石器時代の遠野 |
| ・ | 縄文・弥生時代の遠野 |
| 2.古代の遠野 | |
| ・ | 大和朝廷時代の遠野 |
| ・ | 平安時代の遠野 |
| ・ | 前九年の役・後三年の役 |
| ・ | 奥州文化と藤原氏 |
| 3.鎌倉時代の遠野 | |
| ・ | 阿曽沼時代のはじまり |
| ・ | 交通と文化 |
| 4.室町時代の遠野 | |
| ・ | 南北朝時代の遠野 |
| ・ | 戦国時代の遠野 |
| ・ | 阿曽沼時代の終わり |
| 5.江戸時代前半の遠野 | |
| ・ | 遠野南部氏の政治 |
| ・ | 藩の経済と庶民のくらし |
| <南部藩凶作・水害年表> | |
| 6.江戸時代後半の遠野 | |
| ・ | 遠貨幣経済の発達と一揆 |
| ・ | 産業・文化の新しい動き |
| ・ | 藩政の終わり |
| 7.明治の遠野 | |
| ・ | 明治新政府の諸改革 |
| ・ | 産業の発達 |
| ・ | 上閉伊郡役所 |
| ・ | 遠野商業の停滞 |
| 8.大正・昭和の遠野 | |
| ・ | 恐慌 |
| ・ | 遠野と民俗学 |
| ・ | 第二次世界大戦と遠野 |
| 9.第二次世界大戦後の遠野 | |
| ・ | 戦後の改革 |
| ・ | 高度経済成長と遠野 |
| ・ | 最近の遠野 |
| <遠野の歴史年表> | |
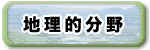
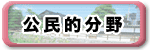

2 藩の経済と庶民のくらし
小友の金山
南部藩は、江戸時代のはじめころ、金山によって藩の財政は豊かであった。 上郷の佐比内にある朴木金山は、特に金の産出が多く、藩に納める税の10分の1だけで年貢米による収入をはるかに超えるほどであった。 遠野でもこのころ、小友に新しい金山が発見され、その領有をめぐって伊達藩との間にあらそいがおこった。各地から金山稼ぎが入り込み、今の小友町のもとがつくられた。金山からの収入は遠野領の財政を豊かなものにした。 しかし、佐比内も小友もまもなく鉱脈がつき、金山景気は長く続かなかった。 また、釜石の橋野鉄山が開発されて、大量の鉄が遠野に運びこまれ、一時は鍛冶業の町として栄えたこともあった。 |
〔近世金山開発図(現岩手県内分)〕 |
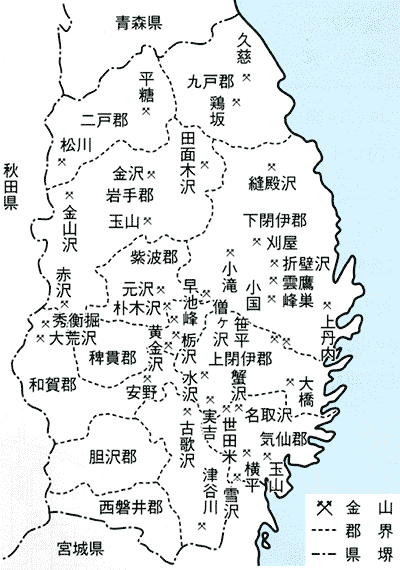 |
〔佐比内の金山〕 志和にあるこの地は、遠野南部領ではあるが、金山経営は盛岡南部家の直山として行われ盛岡藩をうるおした。 旧佐比内村にあった八つの金山のうち、朴木金山は、1620年代の25年間は産金日本一と考えられており、その盛況ぶりを「一山の総人口日ごとに数を増し…13,000人を超え…戸数2,120軒…」と記録されている。(紫波町史) |
藩の専売品
馬は南部藩の専売品であった。農家は、藩から馬を借りて養い、農作業をしたり、物を運搬したり、肥料をつくったりした。子馬はセリ売りして、その代金を藩に納め、手もとにいくらかの収入を得た。地主から馬や牛を借りて養うという馬小作や牛小作もさかんにおこなわれた。優れた馬は、藩が買い上げて他藩へ売ることによって、藩の収入とした。 また、三陸沿岸地方の海産物も南部藩の専売品であり、乾燥した魚介類は、品質もよく他地域で高く取り引きされ、藩の大切な収入源であった。 |
〔馬小作〕 農家は、子馬が生まれるとめす馬はそのまま飼育を許されたが、おす馬は2歳になると藩にとりあげられ、セリにかけられ、売上金の2割が与えられた。そのため、めす馬が生まれると大喜びし祝ったが、おす馬は手離さなければならず悲しんだ。 |
中継商業
江戸時代になると、内陸地方と海岸地方のそれぞれの物資の交流がさかんになり、遠野は、その中継商業の町として発達するようになった。遠野の城下町では、月に6回の定期市が開かれるようになり、「一六市」とよばれた。 市日には、駄賃づけの馬や人夫、商人、近郷近在の人々でにぎわい、「一六市日に馬三千馬…」といわれるほどの盛況だった。 遠野に運び込まれ、通過する荷物からは、「荷役銭(荷振りの口銭)」を徴収する制度があった。一六市日には、荷役銭問屋が置かれ、すべての荷駄はここを通過する時、「おおむね一駄につき30文」の荷役銭が徴収された。 荷役銭問屋の権利は、盛岡南部藩が管理し、上納金の多少によって、それをあつかう商人が決められた。盛岡南部藩が、その権利をしばしば盛岡商人に与えようとしたため、それに反対して、遠野の町人たちは一揆をおこしたこともあった。 |
農民の負担
江戸時代は、年貢米を中心とする「米の経済」といわれながらも、遠野地方は寒冷地なために、麦・ヒエ・アワなどの雑穀中心の農業であった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかし、年貢割り当ては、畑作物も米に換算してのとりたてであった。 村単位に定められた年貢は、さらに村役人が家ごとに割り当てをした。その割合は、一般に「五公五民」と言われ、収穫高の約5割であった。 当時の綾織村の例では、村全体の年貢の平均は、たしかに約5割(47.7%)であったが、水田についてみると、収穫高の6割2分(62%)が年貢として取りたてられていた。 農民は、年貢米のほかに山林・草地・利水・牛馬などや窓・棚などにさえ税をかけられ、きびしく取りたてられた。また、商売でもすれば、運上金という税を納めねなければならなかったし、街道沿いでは、藩の年貢米や専売品の荷物を運ぶ「夫伝馬役」などの労役にもかりだされた。 農民は、村単位で共同で農作業をし、山林や草地も共同で管理した。 ほとんどの農民は、重い税を納めるために副業に励んだ。養蚕・機織り・馬の飼育・炭焼き・狩猟・ワラ細工などをし、それを六度市で売ったのである。また、駄賃づけ(馬で荷を運ぶ仕事)は、定期市の発達とともに、農民の大きな収入となった。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1816(文化13)年の綾織村の年貢負担
「小高面付之覚」より(西登志男蔵) |
▼遠野の民家(重要文化財、菊池家)
 税を免れるために窓も棚もつながった農家。 奥の曲がり部分がうまやになっている。 |
▼重要な副業であった駄賃づけ
 |
あいつぐききん
凶作のために、食べ物がなくなり、貧しい人たちの中に飢え死にするものがでることを「ききん」という。生産を高めれば、それだけきびしく年貢をとりあげられる政治のしくみの中で、農民の生活の苦しさはいつまでも続いた。 だから、冷害などのように自然条件が少しでも悪くなると、そのまま「ききん」に結びついたのである。 南部藩をおそった大ききんは、元禄・宝暦・天明・天保・慶応の5回であった。不作年(4分の1減収)が28回、凶作年(2分の1減収)が36回、大凶作年(4分の3減収)が16回もあったのである。 あいつぐ凶作やききんは、農民の生活や藩の財政に大きな打撃をあたえた。元禄の大ききん(1695年)のころまでは、藩の財政にもゆとりがあったために救民対策も行われ、犠牲者が少なかった。だが、宝暦の大ききん(1755年)の時には藩に米のたくわえも少なく、わずかばかりの救民対策しかできず、南部藩では55,000人以上の餓死者や病死者を出した。 遠野領内でも、餓死者が2,500人以上にもなり、500人以上の人々が領外に逃亡した。当時の凶作は、数年間続くことが多く、人々はしだいに生気を失い、病気で倒れるものも多かった。そのため、田畑は荒れ地になるところが増えていった。 |
| ききんの様子を伝える資料 |
遠野地方の大ききんの様子を記録したものに「遠野古事記」や「動転愁記」等がある。 飢渇人へ救い米・雑穀918駄が支給されたが、死者3千人もあった。そのうち2千5百余は自力で食料を求めかねて餓死した。父母妻子を捨てて行方が知れなくなった者、妻子もろとも家をたちのく者もあり、その数は494人。死馬は2千匹余。 (「遠野古事記」より)
天明の大ききんのとき、南部藩は「ワラの食い方」の触書を出した。「……生なワラを半日水につけ、刻み、石臼で粉にする。ぬかをまぜて、湯をそそいでだんごにし、ゆでてミソをつけて食べればよい……」 宝暦5年の餓死人(「篤吟家訓」巻9)
|
▼飢渇供養塔(松崎)
 松崎町宮代にある。「宝暦七丑年二月七日」の日付と「飢渇死有無縁精霊」。の文字が刻まれている。 |
▼五百羅漢
 愛宕神社の近くにある。天明2(1782)年、大慈寺の義山和尚が餓死者供養のため自然石に彫ったものといわれている。 |
天明の大ききん
天明の大ききんの時は、収穫がほとんどなかった。しかも、藩には対策もなく、お救い小屋の中でも餓死者が出た。最もひどかった東北地方では、毎年の冷害で、米も麦もヒエも豆もとれず、農民はワラやコケも食べ、犬・ネコ・牛・馬も食べた。食べ物がなくなると、人々は飢えをしのぐため、山野に食べ物をもとめてさまよい歩いた。力尽きて息絶えるものも多く、死んだ者を葬る力さえなかった。ききんの中でも最大の被害を記録し、全人口の2割にあたる7万人の死者をだした。 ききんの被害をさらに大きくしたのは、きびしい年貢のとりたてと大商人による米や雑穀の買いしめであった。このために盛岡や遠野では、打ちこわしがおこった。 ききんのたびに、農民や貧しい町人がたくさん死んだ。そのため、江戸時代はいつまでたっても人口が増えなかった。毎年のきびしい年貢の取りたてによって、苦しい生活をしていた農民は、自分の子供も養えなくなり、「まびき」といって捨てたり、殺したりすることもあったのである。 |
宝暦5年の餓死人(「篤吟家訓」巻9)
| 年代 | 戸数 | 人口 | 増加 | 減少 | 摘要 | ||
| 出生 | 入領者 | 死亡 | 出領者 | ||||
| 宝暦 3年(1753) | 62,511 | 355,980 | 6,009 | 209 | 9,923 | 217 | 不作 |
| 〃〃 6年 | 55,667 | 301,686 | 2,047 | 85 | 57,921 | 971 | 大飢饉 |
| 〃〃 7年 | 54,472 | 297.436 | 2.697 | 104 | 8,350 | 1,267 | 飢饉 |
| 明和 4年(1767) | 56,388 | 306,110 | 6,872 | 128 | 6,802 | 253 | 平作 |
| 安永 5年(1776) | 56,430 | 305,859 | 7,675 | 197 | 8,198 | 121 | 〃 |
| 天明 1年(1781) | 56,185 | 406,080 | 8,379 | 314 | 8,389 | 304 | 不作 |
| 〃〃 2年 | 56,074 | 305,831 | 8,448 | 322 | 8,576 | 188 | 〃 |
| 〃〃 3年 | 56,082 | 306,077 | 8,539 | 348 | 8,685 | 202 | 〃 |
| 〃〃 4年 | 45,527 | 245,963 | 7,914 | 226 | 64,698 | 3,320 | 大飢饉 |
| 〃〃 5年 | 45,789 | 246,554 | 8,519 | 328 | 8,621 | 326 | 飢饉 |
| 〃〃 6年 | 45,789 | 245,972 | 8,252 | 297 | 8,881 | 257 | 大飢饉 |
| 〃〃 7年 | 45.938 | 246,778 | 8,976 | 384 | 9,068 | 292 | 飢饉 |
| 〃〃 8年 | 45,927 | 246,144 | 8,672 | 372 | 7,862 | 282 | 凶作 |
| 寛政 1年(1789) | 45,941 | 246,882 | 9,013 | 401 | 9,092 | 322 | 不作 |
| 〃〃10年(1798) | 45.676 | 246.157 | 10.420 | 1,154 | 10.997 | 577 | 平作 |
(新渡戸仙岳編「旧藩時代戸口沿革資料」、篤馬家訓、南部藩雑書)