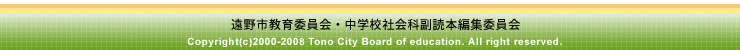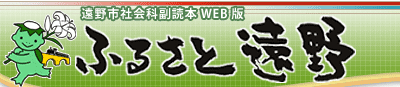 |
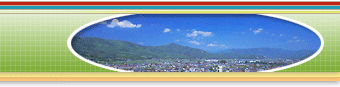 |
||
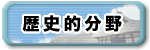
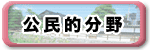

2 遠野の工業と商業
遠野の工業…工業のあらまし
遠野の工業の現状を2010(平成22)年でみると、工場数が65事業所、従業員数は2,189人、出荷額が約376億5千万円である。 遠野の出荷額を業種別にみると、1982(昭和57)年は、第1位が木材・木製品製造業、第2位が窯業・土石製品製造業で、地元産業の出荷額が上位を占めていた。2010(平成22)年は、第1位が生産用機械製造業、第2位が業務用機械製造業、第3位が非鉄金属製造業、第4位が木材・木製品製造業、第5位が繊維製造業となっており、誘致・進出金業の工場出荷額が上位に進出してきている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠野市の主な工場数、従業員及び出荷額等(従業員4人以上の事業所)
(平成22年 工業統計) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、工業の規模は、50人以上の工場は11工場にすぎず、従業員19人以下の工場が60%をしめ、小規模経営の多いことがわかる。 これは、木材・木製品製造業や食料品製造業などのように、比較的少ない従業員数で生産活動のできる工場の多いことからきている。遠野市の1人当たりの出荷額が県や他市と比較して少ない原因の一つが、経営規模が小さく、労働生産性が低いことにあると思われる。 |
遠野市の主な工場
(平成22年 工業統計) 注 Xは事業所の秘密保護のため、 秘匿措置を行っているもの |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
従業員1人当たりの出荷額(単位:万円)
(平成22年 工業統計)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠野の工業…工業の移り変わり
| 戦前、遠野地方に見られた工業といえば、農林畜産物の加工、繊維工業・酒造業・木工業・窯業・鍛冶などで、それらの中には家内工業または副業として営まれていたものがある。 戦後・遠野の工業は、戦前の農林畜産物の加工から食料品製造業へ、木工業も木材・木製品・家具装備品製造業へと、原材料の一次加工から製品化へ変わってきた。窯業も設備の近代化を図りながら発展している。このように、原料、動力源、技術的伝統などを地元にもとめ、発展してきた地場産業を在来工業という。 |
|||||||||
遠野市は1963(昭和38)年に「遠野市工場設置奨励条例」を制定し、工場誘致に力を入れてきた。その結果、衣服、その他の繊維製品製造業や弱電電気器具の製造加工、その他の工場が相次いで誘致され、あるいは進出するようになり、これらの工場から多くの製品が出荷されるようになった。 市は、工場用地の取得に必要な援助をするとともに、固定資産税を免除するなど優遇処置を講じて積極的に工場誘致に乗り出した。その結果、現在は誘致工場が18、進出工場が19となっている。過疎化の防止や雇用の確保につながり、市の工業発展の面で役に立っている。 近年の経済状況により閉鎖を余儀なくされた工場もあるが、遠野の企業の中には最先端の技術を駆使して、情報機器や自動車部品等、様々な製品で使用される部品を製造している企業もある。また、大学との技術提供により製品開発を行いながら、遠野に新しい産業を根付かせている企業や、製造している製品が国内のみならず、世界中で使用されている企業もある。また、食品関係の分野においては、地元の素材を生かして発芽玄米などを製造し、工芸品の分野においては、遠野物語を題材にして遠野産のヒノキの間伐材を利用した玩具もつくられている。遠野の風土や地元の農産物を生かしながら、新しい商品の開発を行い、遠野で製造された多くの製品が県内・全国そして世界に流通している。 |
遠野の主な企業
|
||||||||
〔遠野で工場を経営する方のお話〕 わたしは関東地方からUターンし、地元の遠野で工場を始めました。工場では、主にプラスチック成形品を製造しています。この業界では遠野ではもちろん、県内でもさきがけです。製品はOA機器、自動車、家電、住宅など多種多様な分野で利用されています。また、取引相手先は、東日本の企業だけでなく、西日本、遠くは九州の企業もあります。 コンピュータの発達により、情報についての時間差はなくなりました。また、流通面でも交通網の発達により、製品を運ぶのには時間がかかりません。九州までも2日間で届く時代です。そういう点では、遠野で工場を経営していても不利な点はありません。 これからは、今以上に新しい製品の開発に力を注いでいかなければなりません。わたしの工場では、大学や岩手県とともに共同研究を進め、新製品の開発を行っています。 |
遠野市の製造品出荷額の移り変わり
(旧遠野市と宮守村との数値を合算)
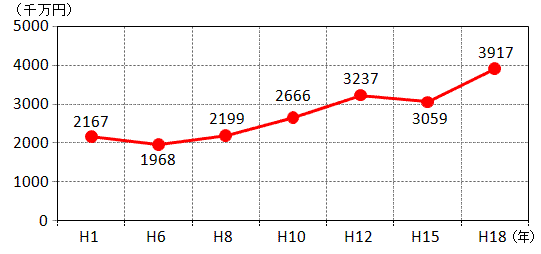 注 H1のみ旧宮守村は平成2年の数値を使用 (工業統計・遠野市勢要覧より) |
工場での生産の様子
 |
遠野の商業…商業のあらまし
| 遠野市の商業について、2009(平成21)年の商業統計でみると、商店数401店で、年間販売額は約332億円(平成19年)となっている。 ここ5年間の統計によると、市全体の人口の推移に伴って、商店数や従業員は減少傾向にある。また、年間商品販売額は経済状況により、着実に伸びているとは言い難い状況である。 県内各地への大型店の進出や、消費者の行動範囲の拡大やライフスタイルの変化により、遠野市外へ買い物客が流出してきている。市外では花巻市・北上市・盛岡市などが買い物先となっている。 遠野市の市街地の商店街は、遠野駅を中心として中央通り、穀町へと南東へのび、比較的広い面積を持っている。駅前にはショッピングセンターもあり、駅前商店街の中心となっている。宮守町では、平成7年に、国道沿いにショッピングセンターがオープンした。 また近年、商業地域として大きく変わりつつあるところが白岩地区である。この地域は市の周辺や市街地から多くの人々が移り住むようになり、新興住宅地として生まれかわったところである。そして、消費人口の増加に伴って商店がつぎつぎに建ち並び、新しい商業地域をつくっている。また、この地域に、学校・消防署・病院・福祉センターなどの公共施設が次々と建てられた。バイパス周辺には大型店やコンビニエンスストアも進出して第2の商業地域となっている。 |
|
バイパスに立ち並ぶ大型店
 |
 |
遠野の商業…商業の移り変わり
1965(昭和40)年ころから、人口流出対策や地域産業の多角化を図るために、工場誘致も進められたが、人口流通にともなう過疎化はすすみ、交通機関の発達と道路の整備、近隣都市への大型店舗の進出などによって、消費者の行動範囲が広がり、年々、市外への買い物客の流出が増えつつある。 |
遠野市中心市街地活性化センター「とぴあ」
   |
整備が完了した下一日市地区
 |
 |