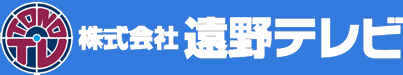2019年5月22日放送
遠野市自主防災組織連絡会会議
 今年度の遠野市自主防災組織連絡会の会議が、きのう(21日・火曜日)総合防災センターで開かれました。遠野市内では、90の行政区のうち、89の行政区で自主防災組織が結成されています。きのうの会議には、各自主防災組織の代表者などおよそ60人が出席しました。はじめに、昨年度の事業報告や、今年度の事業計画案について協議されました。昨年度は、6月に発生した大阪北部地震により、倒壊したブロック塀の下敷きになり、小学生の児童が犠牲となったことを受けて、市内全域を対象に、ブロック塀の安全点検を行ったということです。この結果、対策を講じなければならない危険箇所はなかったということです。また、今年度は、9月1日・日曜日に遠野市防災訓練が実施されるほか、各町で随時、自主防災組織防災研修会が開かれるということです。この研修会は、台風シーズンを前に実施され、ことし6月ごろから、水害・土砂災害について、市町村が出す避難情報と、国や都道府県が出す防災気象情報が「警戒レベル」を用いて発令されることを受け、その周知を図るための説明が行われる予定です。続いての研修会では、大槌町安渡町内会の佐々木慶一会長が「東日本大震災を経験しての地区防災計画の見直し」と題して講演しました。安渡地区では、東日本大震災で、218人もの人が犠牲となり、震災での経験や、浮かび上がった問題・課題をもとに、話し合いを重ね、地区防災計画を策定しました。佐々木さんは、防災計画の見直しを図る中で「助けようとする人の命を守る視点」について挙げ、「共助は重要だが、それだけに頼ると犠牲者がでてしまう。限られた時間の中では、基本は自助が一番大切」と話していました。講演を聞いた人たちからは、「1人でも逃げられるか、玄関まで出てこれるかといった、地域の人たちの状況を把握・確認するところから始める必要がある」「形式的な訓練では意味が無い」などの感想があがり、実のある組織にしていくためにどうしたらいいか、模索していた様子でした。
今年度の遠野市自主防災組織連絡会の会議が、きのう(21日・火曜日)総合防災センターで開かれました。遠野市内では、90の行政区のうち、89の行政区で自主防災組織が結成されています。きのうの会議には、各自主防災組織の代表者などおよそ60人が出席しました。はじめに、昨年度の事業報告や、今年度の事業計画案について協議されました。昨年度は、6月に発生した大阪北部地震により、倒壊したブロック塀の下敷きになり、小学生の児童が犠牲となったことを受けて、市内全域を対象に、ブロック塀の安全点検を行ったということです。この結果、対策を講じなければならない危険箇所はなかったということです。また、今年度は、9月1日・日曜日に遠野市防災訓練が実施されるほか、各町で随時、自主防災組織防災研修会が開かれるということです。この研修会は、台風シーズンを前に実施され、ことし6月ごろから、水害・土砂災害について、市町村が出す避難情報と、国や都道府県が出す防災気象情報が「警戒レベル」を用いて発令されることを受け、その周知を図るための説明が行われる予定です。続いての研修会では、大槌町安渡町内会の佐々木慶一会長が「東日本大震災を経験しての地区防災計画の見直し」と題して講演しました。安渡地区では、東日本大震災で、218人もの人が犠牲となり、震災での経験や、浮かび上がった問題・課題をもとに、話し合いを重ね、地区防災計画を策定しました。佐々木さんは、防災計画の見直しを図る中で「助けようとする人の命を守る視点」について挙げ、「共助は重要だが、それだけに頼ると犠牲者がでてしまう。限られた時間の中では、基本は自助が一番大切」と話していました。講演を聞いた人たちからは、「1人でも逃げられるか、玄関まで出てこれるかといった、地域の人たちの状況を把握・確認するところから始める必要がある」「形式的な訓練では意味が無い」などの感想があがり、実のある組織にしていくためにどうしたらいいか、模索していた様子でした。Copyright(C) TonoCableTelevision. All rights reserved.