| 2015年5月1日(金) 「テミスの求刑」(大門剛明・著)を読む |
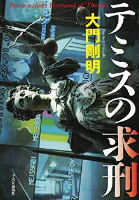 遠野市立図書館の新刊コーナーに似たような題名の新刊本が2冊あった。「テミスの求刑」(大門剛明)と「テミスの剣」(中山七里)だ。テミスって何だろう。アイフォーンで検索してみると、「テミスはギリシャ神話の法・掟の女神、正義の女神とされる」とあり、手には剣と秤(ショウ、ハカリ)を持っているという。後で分かったが、「テミスの求刑」も「テミスの剣」も冤罪を扱うミステリーだった。 遠野市立図書館の新刊コーナーに似たような題名の新刊本が2冊あった。「テミスの求刑」(大門剛明)と「テミスの剣」(中山七里)だ。テミスって何だろう。アイフォーンで検索してみると、「テミスはギリシャ神話の法・掟の女神、正義の女神とされる」とあり、手には剣と秤(ショウ、ハカリ)を持っているという。後で分かったが、「テミスの求刑」も「テミスの剣」も冤罪を扱うミステリーだった。現職の敏腕検事・田島が、なんと殺人容疑をかけられながら逃走し、人質を取って立てこもるという異様な展開に、何度も、え〜!と声を挙げそうになった。誰かをかばっているのか、そしてなぜなのだ。そこには何年も前の冤罪事件が関わっていた。 主人公は検察事務官になって3年目の平川星利奈。彼女の上司が田島だった。揺れ動く彼女の心が田島を裏切る形になり、田島をいよいよ窮地に落とし込む。田島の不可解な行動は、星利奈の父親殺しの犯人とされた男の父親と関わっている、とは彼女も知る由がない。 それにしても、序章の人物、名前が出てなくてどこで絡んでくるんだろうとずっと気になってた。もしかしたら真犯人に繋がる人物か。まさかチョイ役ではあるまい。ラストの数ページで判明するその人物に多少驚くが、検事を辞職したはずなのに、ちょっと作者の強引な結びつけに少しがっかり。 滝川検事対深町弁護士の対決は面白い。ふつうの法廷サスペンスとは一味違い、両者が協同で犯人を暴き出すみたいな展開だが、これはこれで面白い。 本格的リーガルサスペンスだが、主人公・平川星利奈の無茶な行動や守秘義務違反、そして恋人未満の男のことといい、あまり共感を得られず、残念。検事として常軌を逸した田島の行動も、整理して読まないと、なんでそこまですんの?検事がセクハラしてどうすんのよ。 |
| 2012年1月23日(月) 「確信犯」(大門剛明・著)を読む |
| 悪いと分かって罪を犯すこと、それが確信犯だと思っている人が多い。しかし、確信犯とは自らの行為を正しいと信じて行う犯罪のことをいう。道徳的、宗教的または政治的信念を持って、そうすることが正義だと確信してなされる、例えば自爆テロなどは確信犯である。 「違法コピーを行っている大多数の利用者は確信犯だ」とか、「時間を聞きちがえて遅れたと言っているが、あれは確信犯だよね」などのように、悪いことだとわかっていながら行われた犯罪や行為に対して使われるのは誤用である。それでも、「確信犯的に」というのはやや市民権を得ているか。 同様に意味を間違えやすいのに、「情けは人のためならず」、「君子は豹変す」、「流れに掉さす」、「姑息」、「役不足」などもある。言葉は徐々に変わっていくものであるが、これらはまだ、「確信犯」同様に、間違った意味での使い方は市民権を得ていないと思う。正しい意味で使いたい。 さて、ミステリーの「確信犯」。広島で起きた14年前の殺人事件の裁判で無罪放免された犯人は、死の間際に自白する、犯人が自分であると。やがて当時の裁判長や判事が殺されるという連続殺人。果たして犯人は当時小学生だった被害者の息子なのか。その子どもは犯行現場を見ていた。もし彼が犯人なら、彼こそがいわゆる確信犯なのか。 半分ほどまでは面白かった。探偵役なのだろうと思われる主人公もいた。経歴や人間性で十分に魅力的な人物だ。対決軸にいる人物もいる。こいつは絶対ワルだと思う。あるいはこいつが犯人か。たぶん結末は鉄槌を食らわし、溜飲が下がるだろうと期待した。最後までその流れで行ってほしかった。 しかし、途中でそれはないでしょうという展開。なんとその主人公と思われる人物、十分に感情移入できていた主人公が第2の被害者となり、殺されるのだ。そして事件を語る視点がコロコロ変わる。いったい誰が正義で誰が悪なのか。まあ、それはそれでミステリーとして面白いと思うのだが、やはり主人公不明のままの後半はいらいらする。特に人間的も嫌なアイツが主人公のように描かれる後半は面白味が失速する。 司法改革について詳しい。裁判員制度、法テラス、裁判官の増加など、ミステリーを読みながら新しい法制度について少し知ることができた。 |
| 2011年4月6日(水) 「雪冤」(大門剛明・著) 死刑制度を扱う社会派ミステリー |
 ”雪冤(せつえん)”とは、無実の罪を明らかにして汚名を雪(すす)ぐという意味。つまり、”冤罪を雪ぐこと”という、文字どおりの意味だ。同じように屈辱を雪ぐのを”雪辱”という。”雪ぐ”はなかなか読めない文字だが、”そそぐ”とも読むようだ。 ”雪冤(せつえん)”とは、無実の罪を明らかにして汚名を雪(すす)ぐという意味。つまり、”冤罪を雪ぐこと”という、文字どおりの意味だ。同じように屈辱を雪ぐのを”雪辱”という。”雪ぐ”はなかなか読めない文字だが、”そそぐ”とも読むようだ。無期懲役の実刑判決を受けて服役中の人が、その後DNA鑑定の結果、再審&無罪になった例がある。栃木の足利事件、菅谷氏の例だ。その他にも痴漢冤罪など結局冤罪として無罪釈放された人の例は少なくない。 この小説も、死刑囚(八木沼慎一)が「それでも僕はやっていない」と無実を主張し、元弁護士の父親(八木沼悦史)らの推理によりめでたく無罪を勝ち取る、そんな物語だろうと思っていた。ところがところが、そんな単純なミステリーではなかった。 本作は横溝正史ミステリ大賞とテレビ東京賞をダブル受賞した作品だ。綾辻行人氏が絶賛しているそうだが、本格派の綾辻氏が社会派ミステリーを大絶賛するのかな? ちなみに横溝正史ミステリ大賞の賞金は400万円、芥川賞と直木賞は100万円だけ(まあ100万円は副賞みたいなもので、名誉が正賞だろう)。ところが、江戸川乱歩賞の賞金は1000万円、すごい太っ腹だ。 京都で残虐な事件が発生する。被害者はあおぞら合唱団に所属する長尾靖之と沢井恵美。二人は刃物で刺され、恵美には百箇所以上もの傷。容疑者として逮捕されたのは合唱団の指揮者・八木沼慎一だった。慎一は一貫して容疑を否認するも死刑が確定してしまう。 だが事件発生から15年後、つまり時効直前に、八木沼悦史のもとに、「メロス」と名乗る人物から「犯人はディオスだ、共犯の自分も自首したい」と連絡が入る。時効前に何とか真犯人を挙げよう、必死になる悦史や他の関係者たち。しかし、なんと死刑囚・慎一はある日突然、死刑執行されるという急転直下の展開!ここからの後半がこのミステリの本当の面白さとなる。 被害者遺族と加害者家族の視点から死刑制度と冤罪という問題に深く踏み込む。これらにに関して「13階段」(高野和明・著)と比較されるようだが、面白さでは江戸川乱歩賞受賞作の「13階段」の方が読みやすかったし、ずっと面白かった。 「雪冤」、ラストの二転三転のどんでん返しはやり過ぎという批判もある。 P166、「黒目勝ちの瞳」は変換ミス、校正ミス。 |
Hama'sPageのトップへ My Favorite Mysteriesのトップへ