| 2012年5月5日(土) 「銀色の絆」(雫井脩介・著)を読む |
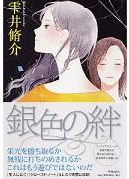 ミステリー作家だと思っていた雫井脩介が、フィギュアスケート界の表も裏もじっくり見せる、こんなスポーツ小説も書くのかとびっくりする。取材と文献参考は半端じゃなく、それに裏打ちされるフィギュア・スケートの精緻な表現力には圧倒される。 ミステリー作家だと思っていた雫井脩介が、フィギュアスケート界の表も裏もじっくり見せる、こんなスポーツ小説も書くのかとびっくりする。取材と文献参考は半端じゃなく、それに裏打ちされるフィギュア・スケートの精緻な表現力には圧倒される。ジャンプには、トゥループ、サルコウ、ループ、フリップ、ルッツ、アクセルの6種類がある。アクセルは前向きに踏切り、他のジャンプより0.5回転多く回転する。だから一番難しいジャンプだ。他は後ろ向きで踏み切るそうだが、違いは分からない。説明されてあったと思うが、覚えていない。 それぞれのジャンプは回転数により、シングル、ダブル、トリプル、クワド(4回転)がある。沙織が練習するのがクワドだ。何度も失敗するが成功するクワドもある。それでも全日本で挫折。オリンピックは夢でしかなかった。しかし、4回転を飛ぶ選手って、女子にいたっけ? 競技終了後、選手とコーチが結果発表を待つ場所をキスアンドクライというのだそうだ。悲喜こもごもの場という意味なんだろう。そういえば、テレビでも何度か聞いた言葉だ。 シニアは15歳以上、ジュニアは13歳以上18歳まで。だから16歳の沙織がシニアを希望してもジュニアに出なさいとコーチに言われる。なるほど、15歳から18歳まではどちらにも出場できるというわけか。 ノービスというクラスもある。10歳以上14歳までということだが、ノービスとはどんな意味なのだ。調べてみたら、noviceで、意味は初心者、つまりbiginnerが同義語だった。 というふうに、フィギュアスケートについていろいろ教えてもらえる小説だ。それでも説明なしには理解できないところもあった。ストーリーの中でさりげなく説明してくれるとありがたいのだが。ジャッジでGOEというのがあったが、これにも説明がなかったようだ。 フィギュアスケートのスポコンもの?最初はそう思った。しかし、スポコンの要素もあるが、サクセスストーリーではない。藤里沙織が友人の千央美に語り掛けながら物語は展開する。つまり回想である。ところが、主人公であるはずの沙織が、物語の中では母親、梨津子に主人公の場を明け渡す。つまり母親の視点で物語は進行するのだ。。 フィギュアスケートは金持ちのステイタスなのか。ステージママたちが娘を送り迎えする車は、競うようにBMW、ベンツ、アルファロメオなど外車。靴や衣装代、リンク使用料、海外遠征費用、外国人振り付け師に払う礼金など、普通の家庭の子どもに習わせるのは無理だ。 沙織の母親も経済的には何不自由なく潤沢だった。夫が浮気、離婚、慰謝料の他に娘の養育費が毎月40万円。名古屋に拠点を移しても経済的になんら問題はなかった。 だが、夫の会社が倒産すると事態は急変する。何とか高校までは沙織にスケートを続けさせたいと、安いマンションに買い替え、車はBMWからコンパクトカーのヴィッツに買い換えた。それでも娘がオリンピックに出られたら、そんな夢を追い求め、娘にすべてを賭けた母親。。 友人でありライバルの希和子が浅田真央をモデルにしたような描写である。オリンピックで銀メダルを取るし、希和子の母親が病死するまでいっしょじゃないか。しかし、この小説の出版日は浅田真央の母親が亡くなるより前だった。つまり作者は真央をモデルにしたような人物を登場させ、予言するかのように彼女の母親を死なせたのだ。 |
| 2005年1月5日(水) 「火の粉」(雫井脩介・著)を読む 今年初めて読んだミステリーは星5つ! |
| 元裁判官で、現在は大学教授を務める梶間勲の隣に、彼がかつて無罪判決を下した男・竹内真伍が越してきた。死刑宣告を受けたかも知れない男であるが、裁判官・梶間によって救われた男である。そんな彼が何のために敢て梶間家の隣に引っ越してきたのか? 愛嬌ある笑顔、気の利いた贈り物、老人介護の手伝い等、竹内は溢れんばかりの善意で梶間家の人々の心を捉えている。しかし、梶間家に徐々に起こる不思議な出来事やトラブル。やがて死者までが。それを竹内と結びつけて考えるのは雪見1人だけだ。 この作品には初めから終わりまで一種の不協和音(サスペンディド・フォーなど?)が底に流れているような感じを受ける。ドキドキさせ、わくわくさせるが、どうも居心地が悪い。落ち着かない。竹内の目的は何なのだ、何かたくらんでいる、あの男は危険だ、だまされている、なぜ気が付かない、陰湿な策略が張り巡らされているじゃないか。早く気付いてくれ、そして早くドミナント・コードに落ち着きたい! いやはや面白い小説だった。越して来た隣人が実は危ない人間だったという怖いストーリーは映画にもよくあるパターン。「隣人は静かに笑う」というミステリー映画があった。ハリソン・フォード主演の「ホワット・ライズ・ビニース」も越して来た隣人が実は〜、といった映画だった。「ケープ・フィア」は、隣人ではないが異常な男が、自分を逮捕した刑事一家を殺そうとする、怖〜い映画だった。 「火の粉」はあの「犯人に告ぐ」(文芸春秋2004ミステリーベスト10国内部門第1位)の著者・雫井脩介(しずくいしゅうすけ)の03年の作品である。雫井脩介という作家はこの「犯人に告ぐ」で初めて知った。劇場型犯罪に対する劇場型捜査がサスペンスフルに描かれ、かなり刺激的だった。読みやすい文章、エンターテインメントに徹したストーリー、スケールの大きな展開等、印象に残る作品だった。 今日読んだ、同じ作者による「火の粉」も、「犯人に告ぐ」に勝るとも劣らず、スリリングでサスペンスフル、そしてもちろん、面白い小説だった。すでに映画化、TVドラマ化が決定しているということだが、ラストの攻防などは実に映画的であろう。「死ねえええええええ!」なんていう表記は劇画的でもある。クライマックスでは読んでいても息遣いが荒くなっているような錯覚を覚えた。 |
| 2004年10月13日(水) 「犯人に告ぐ」(雫井脩介・著)を読む 重厚な面白さに満足 |
| メディアを介して犯行声明や犯人への呼びかけを行う「劇場型犯罪及び捜査」がこのミステリーの主軸を成す。もちろん警察対連続幼児誘拐&殺害犯人が中心に据えられるが、ストーリーに変化を持たせ、この小説をより面白くさせる”対決”はまだある。 子供を犯人に殺された被害者家族対警察である。被害者家族が終盤に牙を剥く。さらに、主人公・巻島はマスコミや世論とも対決する。誘拐犯人を追い詰めながらも逮捕に至らず、挙句に子供は殺害され、迷宮入りとなったことへの風当たりはかなり強い。責任を取らされ降格と異動を余儀なくされる。 対決はまだある。たたき上げのノンキャリア・巻島は警視庁のキャリアとも対決しなければならない。自分より若いキャリアの上司と対決するのだ。ところがその上司は巻島が出演するテレビ会社とはライバル局の女子アナに巻島側の情報をリークさせる。巻島はそのテレビ局と女子アナとも対決する。 このミステリーでは、こういった小説には珍しく家族も十分に描かれる。ラストには安心するが、かなりどきどきする序盤である。父親と妻、娘の出産、その後の危機、孫、などがきわどく描かれ、そして終盤は事件に巻き込まれもする。大きな縦軸に横軸が幾重にも絡みあい、一筋縄ではいかない長編ミステリーである。 ついに巻島がテレビのニュース番組で犯人に宣戦布告する。「犯人に告ぐ。今夜は震えて眠れ」と。終盤のゾクゾクする面白さである。このあたり、メル・ギブソン主演の映画「身代金」(監督:ロン・ハワード)を思い出す。スリリングでありサスペンスフルである。 何度か、おやっ、と思う箇所がある。作者が意図的に読者を、おやっ、と思わせたい部分であろう。他の小説には見られない作法である(と思う)。読者を翻弄させて喜んでいる。憎いね。どういうことかって?読んでみればわかりますよ。 分厚い本で2段組である。最初は長いと思うが、読み始めると止められないミステリー。秋の夜長に最適ですよ。 |
|
|