| 2013年1月11日(金) 逃亡者(折原一・著)を読む |
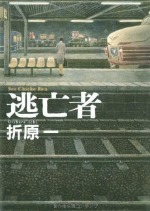 15年の逃亡生活の末時効寸前で逮捕された殺人犯・福田和子(松山ホステス殺人事件)をモデルにしたという逃亡劇。日本各地を逃げ回るノーハウであり、逃亡のマニュアル本みたいだ。 15年の逃亡生活の末時効寸前で逮捕された殺人犯・福田和子(松山ホステス殺人事件)をモデルにしたという逃亡劇。日本各地を逃げ回るノーハウであり、逃亡のマニュアル本みたいだ。いつもの折原一の雰囲気を感じるのは所々にブロック体で挿入される「幕間」。登場する人物が誰なのかは分からない。智恵子の逃亡とどう関わってくるのか。ラストではこれらの意味することが解明されるのだろう。そんな期待を持って読み進めるのだが。。 折原一と言えば叙述ミステリー。随所に読者をだます仕掛けを施しているはずだが、本作品ではラストが折原らしさが出るものの、終盤までは普通の逃走劇だった。 警察と、警察より怖い夫からの追撃をかわし、日本全国を逃げ回る智恵子に読者は感情移入する。ニアミスもあり、智恵子の機転と幸運にも助けられ、スリリングに逃亡する様はこれだけでも十分に面白い。そういえば、昔テレビ番組に「逃亡者」というのがあった。執拗な刑事を追いかけられ逃げる主人公。状況はあれと似ている。 逃走の先々で協力者が現れ、菓子屋のだんなには求婚もされる。顔を整形し、ホステスやスナック従業員として生活しながらも、テレビの公開捜査にはびくびくする。公開捜査の情報により警察からの追っ手を間一髪でかわす。まさに福田和子の逃走劇そのものである。作中でもそのことに触れる。 378ページで読者はあれ?と思う。「ある理由で東京から車で行くことが可能になり、〜」とある。「ある理由で」とあるが、その理由は明記されない。その訳はラストに判明する。作者が「ある理由で」と書くのはフェアではない。ラストのどんでん返しに関わってくるから書けないのであるが、読者はここから違和感を持つ。 さらに、「智恵子は自分の運転免許証はどこにあるのか考えた。そう、警察なのだ」。つまり、智恵子は無免許運転をしているというのか。しかし、この後、運転免許証についての記述はさらに続くが、彼女が運転しているのか、”誰か別の人物が運転しているのか”についての記述はない。これもおかしい。当然ラストの叙述トリック(作者が読者をだます)に関わってくるわけだ。 ラストのサプライズを知りもう一度この辺りを読み返すと、作者の苦肉の策が分かってしまい少々興ざめの部分もある。 それにしてもあのラスト。何度読んでも理解できない所があったが、私の読解力不足なのだろうか。流れに破綻があるようでもあり、すっきりしない。 |
| 黒い森(折原 一) |
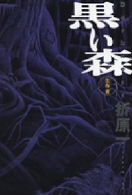 さすが叙述ミステリー第一人者の作品だ。「生存者」、「殺人者」、そして「解決編206号室」の3部から成るが、普通の3部作ではない。「生存者」と「殺人者」は上下さかさまに印刷されており、表からと裏から読めるのだ。おまけに中ほどにある「解決編206号室」は袋とじになる。作者によるとどちらから読んでもいいが、「生存者」から読むのがお勧めだという。 さすが叙述ミステリー第一人者の作品だ。「生存者」、「殺人者」、そして「解決編206号室」の3部から成るが、普通の3部作ではない。「生存者」と「殺人者」は上下さかさまに印刷されており、表からと裏から読めるのだ。おまけに中ほどにある「解決編206号室」は袋とじになる。作者によるとどちらから読んでもいいが、「生存者」から読むのがお勧めだという。まず「生存者」から読む。あるミステリーツアーに参加した訳ありの男女9人と添乗員1人。目的地は樹海、つまり”黒い森”だった。参加者の中の1人が樹里という女性だ。恋人からのメール、「ミステリーツアーの目的地で待つ」を信じてこのツアーに参加した。黒い森の奥深いところにある山荘が目的地だというが、そこはかつてある作家による一家惨殺事件が起こった山荘だった。果たして樹里はそこで恋人に会えるのか。 なかなか面白い設定だ。期待感は膨れ上がり、危うげな登場人物たちと一緒に樹海を歩く気分だ。 やがて、一人、また一人と登場人物たちが消え、あるいは死んで(殺されて?)いく。最後は、”そして誰もいなくなった”なのか。登場人物もちょうど10人だし、アガサ・クリスティのあの名作のパロディなのかと思ったが、違った。山荘にたどり着く人物もいた。盛り上がったところで袋とじの「解決編206号室」となる。 本を引っくり返して、こんどは「殺人者」を読む。樹里の恋人の名前は留美夫だった。家柄の違いで結婚を反対され駆け落ちしようとしている2人。名前がふるってる。留美夫と樹里(エット)かい。アガサ・クリスティから今度はシェイクスピアだ。遊び心満載というわけだ。さすがと言おうかふざけ過ぎと言おうか。 留美夫も樹里から同じメールを受け取り、ミステリーツアーに参加していた。ただし、樹里の参加したツアーから数日後という設定だ。同じように民宿に泊まり、山荘での惨殺事件を聞き、同じように黒い森の中を山荘に向かって歩きだす。さらに同じようにツアー客が次々と姿を消したり死んだりする。 そして留美夫はついに山荘に到着する。山荘で待っていた人物とは?そして「解決編206号室」の内容は?二人のリュックの意味ありげな中身は何だったのか? 読みやすい文、ホラーっぽい内容、上下さかさまの2パート、袋とじ等は作者のアイデンティティか。まずまずの満足度だった。袋とじの内容はそれほど驚愕のラストと言えるほどではなく、リュックの中身も想像どおりだった。それでも折原ファン(私もその一人)にはたまらない作品だろう。一読の価値あるミステリー。 |
| 2010年4月6日(火) 「疑惑」(折原一・著)を読む 短編で味わう折原ワールド |
 叙述トリックの天才、折原一の短編集。短編とはいえそのだましのテクニックは十分に冴える。ひねりの効いたラストも実にいい。これこそ短編らしい短編。日常的な悪を題材としており、最初のページからすんなりと折原ワールドに入っていける。 叙述トリックの天才、折原一の短編集。短編とはいえそのだましのテクニックは十分に冴える。ひねりの効いたラストも実にいい。これこそ短編らしい短編。日常的な悪を題材としており、最初のページからすんなりと折原ワールドに入っていける。「偶然」:振り込め詐欺がテーマ。「オレオレ」に「マサオかい?」。偶然だが詐欺グループの相手もマサオだった。騙される女は1人だと思って読んでいくが、詐欺グループよりもっと悪い女が別にいた。勝ち誇る女がラストにストンと奈落の底に突き落とされるラストが小気味言い。 「疑惑」:引きこもり高校生が連続放火事件の犯人なのか、母親が疑惑を持つ。疑惑を払拭するために夜な夜な外出する息子の後をつける母親。やがて疑惑が確信に変わり、このままでは家族の崩壊だ。そのために彼女がとった行動とは。ラストで分かる真犯人にもびっくりする。 「危険な乗客」:夜行列車で隣り合った女性2人のどっちが連続猟奇殺人事件の犯人なのか。あるいは作者が意図的に描写の視点を変え読者を混乱させようとしているのか。他視点描写、多重文体で知られる折原一のファンなら誰でもそう思うだろう。3人目の女性に注意。 「交換殺人計画」:博之は血の繋がらない父、浩三郎の殺害計画を立てる。両方と通じている女からその情報を得た浩三郎は逆に博之を殺そうと殺し屋を雇う。交換殺人とはお互いの不利益者を殺すこと、完全犯罪の後はもちろん2人とものうのうと生きていく。しかしこの短編の交換殺人とは?結末に笑ってしまう。 「津村泰三の優雅な生活」:ボリュームいっぱいラジカセを鳴り響かせながら布団をたたきまくる騒音おばさん、悪徳リフォーム詐欺、それにオレオレ詐欺という、ワイドショーネタの三位一体ストーリー。悪徳業者を利用し津村の悪事も消えてめでたしめでたしと思うが、ラストにこれまたストン、奈落の底が待っていた。 ボーナストラック「黙の家」とスペシャルエッセイ「石田黙への旅」では折原一の芸術的嗜好が分かる。石田黙という画家について初めて知るが、その作風からして鑑賞したいとは、ちょっと思えない画家。 |
| 2006年10月3日(火) 「チェーンレター」(折原一・著)を読む 不幸の手紙、棒の手紙、そして梓の手紙 |
| 折原一は好きなミステリー作家である。「〜者」シリーズ、「倒錯の〜」シリーズなど、独特の世界に浸れるミステリーであり、今まで読んで面白くないと思ったことは一度もない。だから、本屋でこの作品、「チェーンレター」を見つけたときも躊躇せずに買った。 チェーンレターやチェーンメールはミステリーの題材に相応しい。同じ文面の手紙を5人に2日以内に出さないと不幸が訪れるぞというチェーンレター。もし出さなかったらどうなる。出さなかった人間が次々と殺されたら?ちょっと考えただけでもワクワクするミステリーになりそうだ。それも作者が折原一である。期待は大きく膨らむ。 しかし、何だ、何だ、この不幸の手紙は。「これは棒の手紙です。この手紙をあなたのところで止めると必ず棒が訪れます。2日以内に同じ文面の手紙を5人に出してください」。「不幸の手紙」ではなく「棒の手紙」だった。そして、出さなかった人間は「棒」で殴り殺されるのだ。次から次へと。面白いが、かなり強引な展開だなと思った。 誰でもすぐに気が付くだろう。「不幸」という文字は、偏と旁(つくり)の間にスペースを空けずに少し崩して書くと、「棒」のようになる。この「棒の手紙」をしつこく繰り返す人間はどんな奴だ。やがて、「棒の手紙」が、今度は「梓の手紙」になる。「不幸」や「棒」を崩して書くと、確かに「梓(あずさ)」のようになる。発想の安易さに笑ってしまうが、内容はそんなに軽いものではない。 前半はさすがに折原一だと思わせる展開だった。なるほど面白い推理小説だ。棒の手紙をもらって出さないでいる人間が誰か分かる人間が犯人であろう。当然考えられる推理である。しかし表紙に書いてあるとおり(角川ホラー文庫)、これは推理小説ではなくホラー小説なのだ。途中からストーリーに破綻を起こす。ホラー映画ならごまかしもきくだろうが、小説として読む時はきちんと辻褄を合わせてほしいと思う。 結局、いくら何でもそれは、何が何だかわけが分からない、まあホラーだからごまかされたっていいか、的な終わり方をする。勝手な評価では五つ星のうち2つ、つまり、★★☆☆☆であろう。同じホラーでも先日読んだ「K・Nの悲劇」(高野和明・著)は★★★★★(5つで満点)だった。 折原一はこの作品を最初は青沼静也という覆面作家で出版した。ところがあまり売れなかったようだ。「あとがき」で彼はいみじくも書いている。「文庫化の時も、青沼静也で行こうと思ったら、版元から待ったがかかった。青沼静也では売れない。ハードカバーでは散々な成績だったじゃないか」、と。 それでも映画だったらヒットしそうだ。「リング」や「着信あり」、「呪怨」の路線で、「チェーンレター」。いいじゃないかな。映画化されたら絶対見に行きたい。 |
| 2002年11月11日(月) 「失踪者」(折原一・著) |
| 本格謎解き推理小説なら綾辻行人に限るなんて思っていたが、折原一(おりはらいち)のこの「失踪者」もかなり本格的だ。15年前の事件と現在の事件が交差し、今はどっち?頭が混乱するが作者が読者へ挑戦しているのだ。叙述トリックは彼の独壇場だ。何度も前のページに戻りながらストーリーを整理しながら読み続ける。手紙文、客観的描写、犯人らしき人間の独白等、多重視点による構成は読んでいて飽きることが全くない。登場人物を特定しない描写も読者を翻弄する。読者をバカにするのか!しかし読者は完全に折原マジックの世界に引き込まれる。本当に面白いのだ。 何度も声をあげそうになる。Aだと思っていた人間が実はBだった。現在のBだと思って読んでいると15年前のBだった。15年前のCの犯罪だと思っていると現在のDの仕業だったなど、目まぐるしいカットバックと場面転換である。 そして最後は完全に予想を覆す張本人登場となる。何で?だがよく読んでみると実は考えられるどんでん返しである。第一部で中心的に活躍する人物が第二部ではしばらく登場しない。おかしいなと思っていた。何か鍵を握る人物に思えるが、まさかそこまで、という思いである。 すっかり折原一の叙述トリックにはまった。早速、昨日、「〜者シリーズ」とも言える「誘拐者」を買ってきた。ワンクッションを置いて来週読もうと思う。次に読もうとしているのは、最後は泣けると評判の横山秀夫の「半落ち」である。 |
| 2002年11月23日(土) 「誘拐者」(折原一・著) |
| 横山秀夫の「反落ち」を読みながら折原一の「誘拐者」も読んでみた。先に読み始めたのは「反落ち」だった。最後は絶対に泣けると、評判の新作である。 ところが、先日たまたま入った本屋さんで折原一のこの「誘拐者」を見つけた。「失踪者」で初めて折原一のミステリーを読み、その面白さに圧倒され、気になっていた作者である。即、買って読み始めた。期待通り、読むのもやめられない面白さだった。この作者は折原ワールドとでも言うべき独特の作風を持った人である。 折原ワールドとは、多重文体(地の文に加え、手記、独白、インタビュー、新聞記事などの文体を随所に挿入していく叙述の手法)、非人称主語(彼女は、男は、犯人はなど、それが誰かを明確にしない人称による人物描写)、頻繁に場面を入れ替えるカットバック手法による構成、叙述トリック(犯人が探偵にではなく、作者が読者に仕掛けるタイプのトリック)、そして全編をつらぬくサスペンスとラストのどんでん返しなど、である。 いろんな人物が入り乱れる。正体をカモフラージュした人物描写により、ここに登場している人物が果たしてだれなのかわからない。そしてAだと思っていたら実はBだった、ところが、Bは20年前にBだと思って育てられていたCだった等、この作品でも、「失踪者」で初めて知った折原マジックに翻弄される。 そしてラストのどんでん返しとは?後半部に入り、そのどんでん返しを予想しながら読む。アッと驚くラストがあるはずだ。でもまさかこの人物が関係するようなことではないでしょう。そんなことは絶対ありえることではないと思っていた。しかし、それが実際に起こってしまった時には、その強引さに思わず笑ってしまった。 ラストだけではない。つじつまを合わせようと随所に強引さが見える。やり過ぎの感は否めないが、それでも折原一のミステリーに心から酔いしれる。ミステリーはこうでなくちゃ。それにしても女は怖い。少々スプラッター気味のミステリーで女性向きではない「誘拐者」だった。 |
| 2003年7月29日(火) 「異人たちの館」(折原一・著) |
| 綾辻行人の「館シリーズ」に触発されてか、題名に「館」の付くミステリーを見るとつい買ってしまう。しかも作者は「折原ワールド」として知られ、独特の作風で読者を打ちのめしてくれる折原一(オリハライチ)である。昨年読んだ「誘拐者」、「沈黙者」、「冤罪者」の長編3部作では、その折原ワールドに翻弄され続け、目まいを起こしそうにもなりそうだった。 その折原ワールドの特徴とは、1・多重文体、2・叙述ミステリー、3・長編(600ページを越す)、4・非人称主語(主語が誰だか分からない文章)、など。「異人たちの館」でもその多重文体は健在である。モノローグ、新聞記事、インタビュー、「小松原淳の肖像」と題された年譜、淳が創作した短編ミステリー、雑誌記事、学級新聞、そして本文など。様々な記述から1つの事実を顕にしていく。 そして、あれ?このモノローグはいったい誰?登場人物から考えて当然Aしかいないよな、絶対Aに決まってるじゃない。ところが、ところが、実に合理的にAではなくBになっていく過程。この過程にはえー!っと声を出しそうになる。うまい、なるほど、そう来るのか。 そしてラスト。意外な復讐劇が展開する。それにしても○○○という名前の秘密はすぐに分かりそうなのに気が付かなかった。悔しいな。 残念だったこと1つ。せっかく「赤い靴」の童謡が効果的に使われているのに、それの「見立て殺人」が全くなかったこと。見立て殺人は童謡が挿入されるミステリーの約束事のようなものだと思うのだが。。 |
| 2003年8月18日(月) 「101号室の女」(折原 一・著) |
| 初めて読んだ折原一の短編集。えっ、そんなバカな!心地よく折原ワールドに翻弄され続け、思わず苦笑い。そうだったのかあ。よ〜し、今度はだまされないぞ、こう書いていながら実は〜だろう、これは明らかにミスディレクションだな。と思いながら読んでいくと、ラストにズドン!(突き落とされる)。読者を陥れるワナが二重三重に仕掛けられている。全くもって先が読めない。 「101号室の女」は、モーテル、バス、カーテン、ナイフ、二重人格者。これじゃまるでヒッチコックの「サイコ」だな。 「眠れわが子よ」は準ホラー。子ども殺しの犯人と思わせラストに逆転する展開。初めからもう一度読み返してしまった。 「網走まで」は2人の手紙だけの構成である。手紙は真実と限らない。署名の人(差出人)が書いてるとも限らない。 「石廊崎心中」。”殺人犯を追い詰める主婦”という構図がラストは逆転する。強引過ぎるな。前半アンフェアな記述が多い。 「恐妻家」は交換殺人で妻を殺そうとする2人の男の物語。うまく行くはずがないが、果たして殺されたのは? 「わが子が泣いている」もラスト1ページでドスン、だ。女は怖い。 「殺人計画」でもラストにどんでん返しがある。妻を介して渡す原稿にどのようなトリック・メッセージが隠されているのか。 「追跡」。これもだまされる。彼女と婚前旅行に出かける小心者と人殺しのやくざ。見事なミスリーディングに、やられた! 「わが生涯最大の事件」はラストが二転三転する。本当のラストはちょっとおふざけ。 |
| 2003年11月26日(水) 「倒錯のロンド」(折原一・著) |
| 更級日記で作者の菅原孝標女(すがわらたかすえのむすめ)は、源氏物語を手にして、「はしるはしる、わずかに見つつ、后の位もなにかわせむ」と記す。「はしるはしる」は「走りながら」か、「はしょりながら、つまり、飛ばし飛ばし」の意味なのか。両方の解釈があると、昔、習ったような気がする。いずれにしろ、(源氏物語を読むことは)后の位も何になろうか、后の位なんてどうでもいいわ、と少女は源氏物語にはまってしまう。そして几帳の影で読み耽る。 そんな更級日記のくだりを思い出させるほどインパクトがあったのが、折原一(おりはらいち)の「倒錯のロンド」である。この展開。読むのを止められなくなる。ラスト近く、筆者が読者に挑戦する。「さあ、物語はいよいよクライマックスへ。衝撃的などんでん返しが、あなたを待っています。あなたは、この小説のからくりに気づきましたか?」と。 折原一と言うと叙述トリックの名手。叙述トリックとは作品そのものがトリックになっているミステリで、読者はたいていだまされる。その結果に怒り出す人もいる。だから賛否両論があり、叙述トリックが嫌いな人もいる。だまされることに快感を感じる人は(私もそうだ)、もちろん叙述トリックを好んで読む。 |
| 2003年12月20日(土) 「倒錯の死角」(折原一・著) |
| あんまり意味ないと思うがラストの16ページが袋綴じになっている。立ち読み防止のためか、あるいは絶対に先に読んではいけない驚愕のラストのためか。週刊誌のグラビアも袋綴じの場合、妙に期待感をそそられるものであるが、天下のトリッカー(こんな言葉あり?)、折原一のミステリーのラストにどんな罠が仕掛けられているのか。気持ち的に急かされる。 2冊しか発刊されていないが、「倒錯の死角」は「倒錯」シリーズ2作目だという。一作目は先月読んだ「倒錯のロンド」。倒錯と盗作の語呂合わせが少々軽いが、中身はスピード感溢れ、その展開にぐいぐい引きずり込まれる。ラストは目眩を起こしそう。グルグル回る、まさに倒錯のロンドだった。 この「倒錯の死角」もまた読むのが止められなくなるほど強烈な展開である。アル中のアブナイ翻訳家、やはりアル中のピッカー(こそ泥)、そして201号室の住人OL、その恋人、母親らが登場する。それぞれの一人称描写や日記が多重文体で、時を追って描かれる。折原一の独壇場である。 注目のラスト。トリックが明かされるが、えっ、そんなバカな!なるほど、あれも伏線、これも伏線だったのか。しかし、あのトリックですべてつじつまが合うか?理論的には可能かも知れないが、実際には無理な設定。もう一度初めから読んでみたい気もするが、すべて読み返すのもバカらしい。最初の10数ページほど読んでみる。なるほど、なるほど。見事にだまされたなあ。 |