| 2012年9月6日(木) 「最悪」(奥田英朗)を読む エンタテインメントだね |
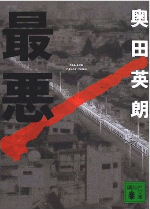 いわゆる群像劇である。群像劇とは、「それぞれの物語」を持った互いに関係のない複数の登場人物がいて、思いがけなく徐々に繋がっていく作品のことを言う。 いわゆる群像劇である。群像劇とは、「それぞれの物語」を持った互いに関係のない複数の登場人物がいて、思いがけなく徐々に繋がっていく作品のことを言う。群像劇と劇が付くが、映画やドラマに限らず小説でも群像劇と言う。単純に登場人物が多い物語を指す用語ではないが、主人公が複数いるような作り方であり、それぞれに関係者や脇役も登場するから登場人物は多くなり、長さも当然長くなる。ミステリーにはよくある手法であり、2年前に読んだ奥田英朗の「無理」も群像劇であり、井坂幸太郎の「ラッシュライフ」なども群像劇である。 ちなみに「それぞれの物語」を持った登場人物がそれぞれに完結する作品はオムニバスと言う。 群像劇は本当に面白くないと、登場人物がごっちゃになったり、人間関係が分からなくなり、長編でもあり、ラストまで読むのがつらいものである。この「最悪」も文庫本で648ページもある。それぞれが主人公にもなりうる主な登場人物は3人いる。町工場の社長川谷、銀行員のみどり、チンピラの和也である。 この3人が最悪に堕ちていく様がスリリングだ。まったく関係ないところでこれ以上ないほど不幸な状況に陥っていくのだ。正直、読み続けるのがつらい。それでも読まずにはいられない。読書にまとまった時間を取れず、空いた時間に切れ切れに読んでいったから、読了するのにかなり日数がかかった。それでもごっちゃにならず、前に戻らず読み進めたのは、とにもかくにも面白いからである。 3人の中で一番感情移入できるのは町工場の社長・川谷だ。彼の周りに現れる人間たちとその行動に読者は強い反感を感じる。危うい儲け話に設備投資、銀行からの資金融資。地域民との対立と嫌みな自治会代表者に弁護人。うまい話しに乗ってはだめだと思うが、そこで立ち止まったのではストーリーとして面白くない。ずんずんと川谷は地獄を目指す。 チンピラの和也は金儲けのためにやくざと絡むことになる。痛めつけられ逃走し、少女と出会い、「明日に向かって」みたいに2人で銀行強盗もやってしまう。出来過ぎのようにやくざの目をくらまし、逆に相手をやっつけ、警察からも逃げる、逃げる。やくざからのリンチ場面で痛いシーンが何度か出てくるが、息を呑む残酷描写に奥田英朗の表現力の高さを感じる。 銀行員のみどりへのセクハラや怪文書の騒ぎはこの2人に比べたら大したことではない。本人は銀行を辞めることを考え続けるが、本当の最悪はそんなことではなかった。自分が勤務する銀行になんと自分の妹がチンピラの和也と一緒に強盗に押し入るのだ。最悪だ。 そして4人は逃げる。残された道は最悪の最悪でしかない。生きていてもこの先希望も何もない。死ぬしかないのか。果たして結末は?ジャジャーン、とまあ、こんなストーリーである。 ラスト、一縷の望みも光明も見いだされる結末に少し安心する。まあ無理やり感は否めないが、最悪のまま登場人物が全員死んで、はいおしまい、ではなくてよかった。奥田英朗はよくもまあこんなストーリーを考えつくものだ。 |
| 2010年5月11日(火) 「無理」(奥田英朗・著)を読む |
 合併でできた、ある地方の小都市”ゆめの市”に住む5人の人間。全く関係ない5人の生活が交互に描かれる。それぞれがドラマチックに展開し、やがてどの人間も追い詰められ破滅に向かう。それぞれが単独でも面白く、短編小説を5冊も読んだ感じだ。 合併でできた、ある地方の小都市”ゆめの市”に住む5人の人間。全く関係ない5人の生活が交互に描かれる。それぞれがドラマチックに展開し、やがてどの人間も追い詰められ破滅に向かう。それぞれが単独でも面白く、短編小説を5冊も読んだ感じだ。相原友則は市の社会福祉事務所で生活保護を担当し、巡回指導するケースワーカーだ。仕事は真面目に遂行するが、ある時から主婦の援助交際にはまっていく。それも勤務時間中にだ。やがて信じられない恐怖を体験することになる。映画「激突」のように。 久保史恵は東京の私立大学を志望する高校2年生。塾にも通う普通の真面目な女子高生だが、引きこもり男性に拉致され、離れに監禁される。5人の中ではただ1人の被害者だ。加害者のノブヒコはネットゲーマーで二重人格者のようだ。悲惨な監禁生活は恐怖との戦いだ。 加藤裕也は暴走族上がりで詐欺まがいの商品を売りつける悪徳セールスマン。元ゾクの先輩、柴田の社長殺しに巻き込まれ、死体を車のトランクに入れたまま数日を過ごすことになる。こいつらは自業自得だ。同情なんかしない。早く警察に逮捕されろ。 堀部妙子はスーパーの保安員をしながら新興宗教にすがる48歳のオバサン。対立する宗教団体のわなにはめられ保安員はクビになり、兄がめんどうを見ていた実の母親の介護もしなければならなくなった。歯車の狂ったその後の生活は破滅に向かって一直線だ。 山本順一は市会議員。県議員に打って出る腹積もりでいる。業者との癒着、暴力団との関係、不倫、放蕩妻、産廃施設への反対運動など身辺はたたけばいくらでも埃が出る。なんとかうまく立ち回っていたが、産廃施設建設反対運動の女性リーダーを山本が関わる業者が殺してしまう。このままでは捜査は自分にまで及ぶ。 このタイプのミステリーでは普通、関係ない人物が物語の途中から繋がってくるものだが、「無理」ではいつまでたってもそれぞれが独立した物語として進行する。交わってこないのだ。おかしい。こんなはずでは。 そしてラスト。500ページを越えた辺りで作者のたくらみが分かってくる。5人が一度に関わってくるのがこのラストだけ。5人が5人とも追い詰められ、ある状況の下に一同に会すということになるが、もちろん普通の状況ではない。 あの5人に普通のラストなど考えても「無理」だったのだろう。面白いが後味は苦々しい。 |
| 2005年12月7日(水) 「サウスバウンド」(奥田英朗・著)を読む |
| 「サウスバウンド」ってどんな意味?Southは沖縄を言うとして、①弾みで沖縄に行ってしまうの意味か(bound跳ね上がる、弾む)、②南限の地、沖縄のことか(bound限度、境界)、それとも③沖縄へ向かうという意味なのか(bound~行きの、~に向かう)。 ブログなどを読むと、①の意味と思ったが、②の意味だろうという意見があった。本文中で解説されてはいないが、私は、③の意味だと思う。Southbound、簡潔な日本語で表すと、北帰行ならぬ、「南帰行」である。 304ページまでの第1部では東京中野が舞台である。元過激派だった、一風変わった父親がいる。今でも権力と戦うことを生きがいとし、毎日ゴロゴロしている。以前人を殺した(と、いじめっ子が言っていた)母親がいる。彼女も元過激派だったらしいが、今では普通の女性だ。恋人がいるらしい姉。第1部では無愛想であるが、第2部ラスト付近で変身、再登場する。金持ちにあこがれる妹。おばあさんを尋ねて会いに行く、いじらしい妹だ。そしていじめにあいながらも元気な僕、二郎。日々成長する明るい小学6年生だ。友人も多い。 第1部では、二郎の目を通して、家族や学校、教師、友人たちを語る。いじめ、けんか、逃避行、別れなどがあり、随所に笑いと泣きが入る。まさにエンターテインメント、面白い小説である。直木賞受賞作家、奥田英朗、渾身の傑作長編と言える作品であろう。一気に読めそうだった。父親や母親の過去が明らかになるだろう第2部に一気に突入、と言いたいところだったが・・・。 しかし、沖縄が舞台となる第2部で途中、しばらくもたつくのはどうしてか。ラストの活劇風クライマックスまでが長すぎると思う。当然だが、第2部では家族を取り巻く人間がすべて入れ替わる。読者がこの切り替えをスムーズに行わないでもたもたしているとそんな風に思ってしまうのか。 新たに関わってくる人物は、もちろん素朴で親切な沖縄の人たちである。ほとんどが善人である。父一郎の生い立ちや祖先について、村人たちの言動から次第に分かってくるが、なんとミステリアスな父親だったことか。 やがて、元過激派だった父一郎の出番がやってくる。リゾート開発業者との反対闘争に巻き込まれてしまうのだ。始めは非常識な、頼りない人間だった父親の主張が、最後には説得力を持ち、彼の人間性までが違って見えてきたりする。ハチャメチャな大人だと思っていた父一郎が実はとっても純粋だったのだ。そして東京から沖縄に来る姉。彼女の出生の秘密が分かり、母親さくらが人を殺したという過去も分かる(出生の秘密も殺人も暗いものではないのでご安心を)。 やがて、ストーリーは結末に向かう。途中のダラダラ感はあるものの、読後は深い余韻の残る傑作である。 |
|
|
Hama'sPageのトップへ My Favorite Mysteriesのトップへ