| 2018年1月25日(木) 「風神の手」(道尾秀介・著) |
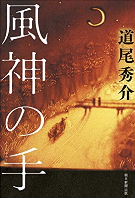 遺影専門の写真館、鏡影館を訪れる人たちを巡って繰り広げられる連作ミステリ。それぞれが単独にまとまった、「心中花」、「口笛鳥」、「無常風」、「待宵月」の中短編4作からなるが、それらが数十年の歳月を経て 登場人物がすべて繋がる。道尾秀介ワールドが心に染み入る。 遺影専門の写真館、鏡影館を訪れる人たちを巡って繰り広げられる連作ミステリ。それぞれが単独にまとまった、「心中花」、「口笛鳥」、「無常風」、「待宵月」の中短編4作からなるが、それらが数十年の歳月を経て 登場人物がすべて繋がる。道尾秀介ワールドが心に染み入る。ちょっとした神の悪戯か、一陣の風が巻き起こした悲劇が、様々な人たちに影響を与え、長い年月を経て次々に判明してくる第3章から、おっ、あれ?と思わせながら、終章へと流れる、そんな作風は作者の真骨頂。それぞれの物語が伏線だらけで、最後にすべてが繋がって、めでたし、めでたし。 第1章、第2章をまったりとした気分で読んでいくと、第3章で分かってくる新事実。ほんわかとした雰囲気でイージーリスニングならぬイージーリーディングと思いきや、その先入観にそぐわないストーリー展開に驚く。時にサスペンスフルであり、シリアスなミステリーともなるのだ。こんなミステリ、他に誰が書く? |
| 2013年1月4日(金) 御用始め 「カラスの親指」(道尾秀介・著)を読む |
| 詐欺師の武沢と相棒のテツ。以前は2人とも普通の男だったが生活苦から闇金に手を出し、家族を失い、人生を狂わされた。この2人の借家に2人の姉妹と妙な男、さらに1匹が転がり込み、5人+1匹の奇妙な生活が始まる。そして、残酷な過去にけりを付けるため、彼らは人生の大逆転を目指し、自分たちを陥れた闇金融グループにド派手なペテンを仕掛ける。そして大団円を迎える・・?、のか。 冒頭から、ん?と思う。銀行帰りの男に仕掛けたこの詐欺はどう考えても成功していない。14ページだ。テツはどうやって金を受け取ったのだ。何度読み返してもその経過が書いてないし、時間的にも論理的にもこの展開は無理だ。道尾秀介の手抜きか、仕事のし過ぎによるケアレスミスなのか。 そんな腑に落ちないことがそれ以降も何度かあった。 詐欺師が主人公のこのミステリー、作中の詐欺師が闇金グループにペテンを仕掛けると同時に、道尾秀介は読者にペテンを仕掛けていたのだ。冒頭から感じる、これらの違和感が見事にラストで腑に落ちる。我々もだまされていたのだ。なるほど、そうだったのか。作者の道尾秀介はすごい。あのような書き方がフェアでそれ以上でもそれ以下でもアンフェアになる、ギリギリの所で読者に違和感をもたらしていたのである。 目次は全て英語で、Heron(サギ)、Bullfinch(ウソ)、Cuckoo(カッコー)、Starling(ムクドリ)、Albatross(アホードリ)、そして、Crow(カラス)の6章からなる。詐欺師のことをCrowと言うのだそうだ。それも、ダジャレだと思うが、クローだけに玄人の詐欺師だ。 親指の逸話は面白い。お父さん指(親指)は、お母さん指、お兄さん指、お姉さん指、赤ちゃん指と簡単にくっつく。お母さん指は中指、薬指には何とかくっつくが、小指にはくっつきにくい。母親と子どもはうまく寄り添わないということか。 しかし、親指と人差し指をくっつけて、同じことをやると、小指は難なく人差し指とも簡単にくっつく。「どっちも揃ってんのが、やっぱり一番なんですよ」 そして、ラストにもう一度指の話。「親指だけが、正面からほかの指を見ることができるんです。全部の指の中で、親指だけが、ほかの指たちの顔を知ってるんです」、テツさんが言う。親指はテツさんだった。 前半から中盤まで、登場人物たちの暗い過去が描かれる。誰一人として夢も希望もない人生を歩んでいる。しかし、ラストで二転三転し、オセロの黒白がガバッと逆転するような展開に読後感はいい。うまくいきすぎだよ、というツッコミはミステリーには要らない。阿部寛主演で映画化もされ(昨年11月公開)、最近まで上映されていたと思うが、DVDが出たら借りて観たいと思う。 |
| 2011年1月24日(月) 第144回直木賞受賞作「月と蟹」(道尾秀介・著)を読む |
| 直木賞候補に5度連続ノミネートされ(記録だという)、5度目の正直、みごと直木賞を受賞した道尾秀介氏。その作品はミステリーでなかった。ホラーでないもないし、青春ものでもない。小学生3人が主な登場人物であるが、もちろん児童文学でもない。直木賞は読み手を大人対象とする文芸賞なのだ。 小学5年生の真一が主人公。父親は病死し、パートで働く母親と祖母と3人で暮らす。学校での唯一の友人は春也だ。春也は父親から虐待を受けているようだ。2人は他の児童とはほとんど交わりがない。海辺でヤドカリを取っては山を登り、ヤドカリを彼らのアジトに運ぶ。そこは2人だけの秘密基地みたいな所である。時にはある”儀式”で”ヤドカミ様”に願い事を掛けるが、それがたまたま叶う。たまたま?いや数回願いが実現する。 徐々に、2人に加わる少女が登場する。母を亡くした少女、鳴海だ。その事故には真一の祖父が関わっている。3人は毎日のように海に行きヤドカリを取り、アジトに運び飼育(?)し、ヤドカリと戯れる。やがて、1人の少女をめぐる2人の男の子の心の動きが出てくる。小学校5年生である。恋愛感情以前の心の揺れである。 そんな内容で物語は淡々と進む。盛り上がりもない子どもの世界のストーリー。そんな小説を大人が読んで楽しいのか。これが直木賞受賞作かとページ数半分を過ぎるまではそう思って読んでいた。後半にやっと物語りに目立った動きが出てくる。この作品は絶対に最後まで読もう。 真一の母親が土曜日の夜に家を空けることが多くなった。誰か男性と会っているようだ。相手は鳴海の父親のようだ。確かめるべく、真一はある行動に出る。お互いに配偶者を亡くしている2人だから、会っていようが何しようが問題ではないが、真一には許せない。もし2人が結婚すれば、真一と鳴海はきょうだいということか。 作者は子ども3人の心情表現がうまい。小学生が大人の世界、大人の問題にに近づき過ぎず、離れずといった危うい関係をうまく描き出している。祖父の何気ない一言が重みを持ってくる。母親の切ない嘘をさらりと流す。 最初から最後まで真一の視点を通して語られる物語である。ラストは優しい、暖かい。余韻が残る。これこそ道尾ワールドだ。直木賞より芥川賞という雰囲気の作品であると思った。 |
| 2010年3月22日(月) 「球体の蛇」(道尾秀介・著)を読む |
| 遠野市立図書館で借りてきた本。道尾秀介の作品だからジャンルはミステリーかホラーかと思った。題名の雰囲気から(気持ち悪そうだから)むしろホラーの方だろうと思った。 しかし、そんな思い込みはすぐに心地よく裏切られた。道尾秀介には珍しい文芸作品調、青春小説だった。もちろん道尾秀介らしい味付けが施され、トリックとは言えないだろうが、イントロダクションの内容と、表紙の装丁にちょっとした秘密があり、”らしさ”を感じた。 「見慣れた冬景色が音もなく反転した」で始まるイントロダクション。この文章以下10行ほどの意味が理解できず何度も読み返した。作者はどんな情景を読者に与えようとしているのか。大学入試の現代文の問題を解くような気持ちで何度も読み返した。しかし分からない。 結局分からないまま第1章から読み始めた。理解できなかったイントロダクションの文章などすっかり忘れてすぐに内容に引き込まれた。 主人公友彦(17歳)が語る一人称小説である。親の離婚により友彦は橋塚乙太郎一家に居候している。乙太郎の妻はキャンプ場の火事で死亡し、2人姉妹の姉サヨも火傷の後遺症が原因でか、自殺した。 やがて友彦はたまたまサヨに似た女性(智子)と出会い、一方的に慕うようになる。智子が入って行き翌日まで出てこない家のことが気になる。友彦はその家の床下に忍び込み、初老の男と智子との情事らしい声を盗み聞く。高校生がそこまでするかとツッコミを入れたくなるが、このあたりの展開は江戸川乱歩を思わせる。倒錯愛の物語なのか。いや、そうでもなかった。 ミステリーではないが、この本ではよく人が死ぬ。智子の相手の男が火事で焼死し、しばらく経つと智子が自殺したと聞かされる(真偽は分からない)、そしてラスト近くには乙太郎も病死する。自殺の原因は、そして2つの火事の原因は何なのか。それぞれの登場人物が火事は自分の責任であり、自殺は自分が殺したようなものと語るが、誰が本当のことを言い、誰がうそをついているのか、作者はあえて明らかにしない。 友彦は大学生になり、卒業し、その数年後、結婚もする。ラストはイントロダクションに繋がるようだ。改めてイントロダクションを読む。また新たな切なさが湧き上がり、読み終えた余韻に浸ることができる。そして理解できなかった「見慣れた冬景色の反転」の意味が分かる。そうだったのか。心にジンと響くイントロダクションだったのだ。 さらに表紙と裏表紙のデザイン。よく見れば雪景色が描かれているではないか。よく見ないと気がつかない、だまし絵みたいな表紙だ。これが内容と関わってくるし、奇妙な題名の意味にも関わってくる。 直木賞候補の最後の何作品かにまで残った作品だというが、なるほどいい作品である。不満は田西オサムと相手の女性の扱い方。結局、あの2人はストーリー上どんな役割だったのか。よく分からなかった。 |
| 2010年1月27日(水) 「竜神の雨」(道尾秀介・著)の感想 |
| 全国のミステリー通、書店員が選ぶ!2009ミステリーベスト10の第9位にランク付けされている作品。ちなみに、同じ道尾秀介の作品、「向日葵の咲かない夏」は2009年度文庫ミステリーベストランキング第1位となっている。 19歳の添木田蓮と中学生の妹・楓の兄妹がいる。父親とは離別、再婚した母親は事故死。今は継父である睦男と3人暮らしだ。ある日、楓の様子がおかしい。酒におぼれ仕事もしないで一日中家に居る睦男だが、楓が睦男に何かされたらしい。レイプか。疑惑が確信に変わった時から蓮の中に睦男に対する殺意が沸き上がる。 もう一組の兄弟がいる。中学生の溝田辰也と弟の圭介だ。母は水難事故で亡くなり、父も病死した。こちらは継母の里江と3人暮らしだ。里江は2人に優しいが辰也は里江に心を開かない。大型の台風の影響で雨が激しく降る夜、蓮が勤める酒屋に、辰也・圭介兄弟が万引き目的で入店する。ここから2組の兄妹、兄弟がクロスする、とても切ない物語が始まる。 ドキドキ感が素晴らしい。十分にサスペンスフルだ。先の見えない暗いストーリー、いったいこの兄弟らに救いはあるのか。どうしようもない結末を迎えるだけなのか。この子らに少しは救いの手を差し伸べてくれよ、そう願った。 しかし、さすが道尾秀介。中盤から意外な展開を見せるのだ。これぞミステリーの醍醐味という展開だ。読者は完全に翻弄され、そうだったのか!昨日は東野圭吾の小説に似た作風だと書いたが、あの幾分ホラーっぽくなる展開はやはり道尾ワールドと言えるものだろう。人物描写が怖いのだ。 あの人があれだと分かった後はもう読むのが止められない。一気にラストまで読んでしまった。切ない兄弟らに少し明るさが差し込むラストにほっとする。決してハッピーエンドではないが。どうやらあの110番電話はつながらなかったようだ。大雨が恵みの雨になったのか。 普段あまり小説など読まない人にもお薦めですよ。途中で止めることができなくなる小説です。 |
| 2009年6月24日(水) 「向日葵の咲かない夏」 ホラー的ミステリー |
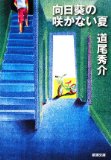 さすが、「このミステリーがすごい!」2009年度版作家別投票第1位。東山堂盛岡駅前店でも目立つ所に平積みにされていた。 さすが、「このミステリーがすごい!」2009年度版作家別投票第1位。東山堂盛岡駅前店でも目立つ所に平積みにされていた。小学4年生の僕(ミチオ)は、1学期終業式に欠席した友人Sくんの家を訪問し、Sくんの遺体を見つける。連絡を受けた岩村先生と警察官が現場に急行するが死体は消失。警察はSくん行方不明事件として捜査を始める。 1週間後、ある物に生まれ変わったSくんがミチオの前に現れる。Sくんが言うには、「自殺に見せかけ僕を殺したのは岩村先生だよ。遺体はどこかに隠されているんだ。お願いだから僕の身体を見つけてほしいんだ」 おいおい、真面目なミステリーだと思っていたのに、これはファンタジーだったのかい。そして始まる僕と妹ミカ、それにある物に姿を変えたSくんの探偵ごっこ(君たちは少年探偵団かい)。岩村先生犯人の証拠を見つけるために先生のアパートにしのび込み、教師にあるまじき岩村先生の性癖を知る。岩村先生は卑猥な内容の本をあるペンネームで出版していることも判明する。「少女」(湊かなえ・著)に出てくる、教え子の作品を自作として出版し、買春するあの悪徳教師みたいだ。 構成は僕という一人称で書かれるパートが大半だが、三人称視点の描写が時々挿入される。中盤までは犯人=岩村先生の叙述ミステリーだと思ったが、後半は一転する。岩村先生はどこにも出てこなくなる。犯人は?そして死んだはずのSくんの扱いはどう説明される? 10歳とは思われない推理を展開する僕と、3歳とは思われないアシスタント的妹、そしてある物に姿を変えたSくん。そもそもロジックが本道のミステリーで死んだ人間の生まれ変わりなどあっていいはずがない。そのSくんの存在に他の登場”人物”たちが違和感を持たず普通に会話するってのはどうにも解せない。いったいどういうけりをつけるつもりなんだ、この作者は。 「幽霊刑事」(有栖川有栖・著)では同僚に殺された刑事が、幽霊になって事件を解明する推理小説だった。ミステリーにこんなばかばかしいのもありなのかと思ったが、この「向日葵の咲かない夏」も最初は同じように感じていた。 しかしこの作品はおちゃらけではない。ある物に生まれ変わったSくん、妹ミカの出生秘密、クラスメート・スミダさんのこと、狂ったお母さんの溺愛する妹ミカ(ミチオの妹ミカと同一人物のはずなのに・・)、トコお婆さんの生まれ変わり、泰造じいさんの秘密など、読み終えるともう一度読み返したくなる。伏線が心憎い。ああ、そうだったのかと、読者はだまされる。 絶対に映像化できないミステリーである。文字で書かれた小説ならではだましのテクニック、つまりトリックである。歌野晶午の「葉桜の季節に君を想うということ」や「女王様と私」のトリックに近い。 |
Hama'sPageのトップへ My Favorite Mysteriesのトップへ