| 2015年1月12日(月) 「悪の経典」(貴志祐介・著)を読む 面白いことは面白いが。。 |
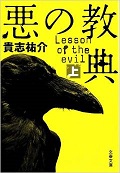 文庫本で上・下巻あり、かなりの長編である。それでも飽きることはなく読み耽った。登場人物が多い。校長以下教職員、主人公が担任するクラスの生徒たち、保護者や警察など。 文庫本で上・下巻あり、かなりの長編である。それでも飽きることはなく読み耽った。登場人物が多い。校長以下教職員、主人公が担任するクラスの生徒たち、保護者や警察など。上巻でも主人公のサイコパス(反社会性精神病質者)ぶり、キラーぶりは徐々に描かれるが、上巻までは単なる序章だった。後半は怒涛、まさに怒涛の阿鼻叫喚となる。 主人公の蓮実聖司は東京都町田市にある私立高校の英語教師。さわやかなイケメンで頭が切れ、ハスミンというニックネームで慕われている。大学は京都大学からハーバード大学卒業という高学歴の教師だ。そんな彼だが住むところはボロ屋であり、通勤に使う車はハイゼット、つまり軽トラだ。 えっ、軽トラの英語教師、って言うと、昔のオレだってそうだった。しかし、己の過去の姿を主人公に被せて昔を思い出す、そんな悠長な物語ではない。出だしは高校を舞台とした昔の青春ドラマのようだった(ここまでは昔のオレにイメージを被せていた)が、なんとなんと、主人公をはじめ、この高校の教師たちは狂ってる。こんな教師がいるもんか。 蓮実は自分が担任するクラスの美少女と関係を持つ。学校では屋上で、普段は弱みを握った美術教師のマンションで、修学旅行ではホテルの一室に呼び出しことに及ぶ。お泊りデートにいくらなんでも軽トラは使わない。金持ち美術教師の愛車、ポルシェを強制的に使う。 その金持ち美術教師(久米)は同性愛者だ。その相手とは蓮実が担任するクラスの男子生徒だった。こちらも相思相愛のようだ。美術室や、やはり修学旅行先のホテルで密会を繰り返す。それを知った蓮実は久米を脅迫する。男との逢瀬に使うマンションも取り上げる。久米はもちろん蓮実の裏の顔を知らない。 養護教諭の田浦潤子もぶっとび教諭だ。保健室で男子生徒や蓮実の性的な求めに応じるのだ。早水圭介は優秀な2年生だが、麻薬常習であり、時々保健室に行って田浦と性的な関係を持つ。それも勤務時間中、保健室のドアにカギもかけずにだ。まあ、その間中、保健室には誰も来なかったというのはご都合主義だ。 体育教師の芝原は女子生徒の万引きをネタに脅迫し、教官室に呼びつけセクハラを繰り返す。休日や夜、誰もいない校舎に忍び込んで女子生徒を呼び出し、良からぬことをしでかす。 教師が教師なら校長も校長だ。灘森校長は10年前まで数学教師釣井の妻と不倫していた。釣井は校長の目の前で妻を殺害し、死体を自宅の床下に埋める。その時、校長に穴を掘らせ死体を埋めさせた。つまり校長が死体遺棄したが、釣井の妻はその後失踪ということで事件はばれなかった。釣井は数学の指導力も信頼もない不適格教員だが、弱みを握られた校長は釣井に何も言えない。 生物の教師・猫山は生き物が大好きで、特に死体は喜々として解剖する教師だ。蓮実が殺したカラスや犬を提供され狂ったように解剖を始める。 上巻だけでも蓮実は何人殺したのだろう。両手でも足りない。同僚教師にモンスターペアレント、前任校の都立高校でも生徒4人、子どもの頃両親、アメリカ時代の同僚、中学校時代の担任など、など。 そしてミステリー風だった上巻は、下巻となってホラーノベルと化す。殺して殺して殺しまくる。まるでゲームのように、文化祭の準備で学校に泊まることになっていた生徒全員を殺すのだ。2人、いや3人が結局生きていたが、あとは全員殺す。美術教師も体育教師も殺す。退学してその晩に学校に来た生徒も殺す。 命乞いをする東大志望の成績優秀な生徒に言う。You are going to Todai?No,you are going to die.(東大に行くって?いや、死ぬんだよ)には笑ってしまった。 |
| 2010年2月21日(日) 「青の炎」(貴志祐介・著)を読む 倒叙ミステリーも好きだ |
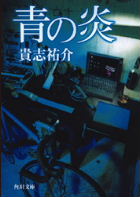 普通のミステリーでは、まず殺人事件が起こり、警察(あるいは探偵役)が捜査に乗り出し、犯人の行動や動機を推理しながら事件を解決する。意外な犯人がラストに判明し、犯人は動機やトリック等の詳細を自白して終わる。これが一般的な推理小説のパターンである。 普通のミステリーでは、まず殺人事件が起こり、警察(あるいは探偵役)が捜査に乗り出し、犯人の行動や動機を推理しながら事件を解決する。意外な犯人がラストに判明し、犯人は動機やトリック等の詳細を自白して終わる。これが一般的な推理小説のパターンである。これとは逆に、まず犯人がいてやむにやまれぬ動機から殺人を犯す。警察や探偵の側が捜査を開始し、小さな穴から徐々に完全犯罪が破綻していく。つまり、事件を犯人側から描いたもので、ストーリー展開が普通のミステリーと全く逆になる。これが倒叙ミステリーである。松本清張の短編や刑事コロンボにこのジャンルが多い。 さらに叙述ミステリーと呼ばれるものもある。犯人が探偵や警察や仕掛けるトリックではなく、作者が文章構造上のトリックならぬレトリックで(女だと思って読んでいたら実は男だったなど)読者にトリックを仕掛ける。読者は騙される。私が読んだ中では折原一や歌野晶午の作品に多い。 「青の炎」は典型的な倒叙ミステリーである。犯人は成績優秀な高校生、櫛森秀一だ。ターゲットは母親が10年前に別れた再婚の男、曾根だ。曾根は自堕落な生活を送り、母親を恐喝し、中学生の妹にまで手を出そうとしている。このままでは家族は崩壊する。あいつを殺るしかないのだ。 この展開は最近読んだ「竜神の雨」(道尾秀介・著)と同じだ。そういえば、櫛森がコンビニでバイトをし、コンビニが重要な事件のスポットであることも、終盤、豪雨の中で物語が進行する展開も似ている。別れた夫が元の妻のところにやってくるのはよくあるパターン。東野圭吾の「容疑者Xの献身」もそうだった。 倒叙ミステリーでは殺人が完全犯罪のまま終わってはならない。必ず犯人があがらなければならない。この作品では高校生櫛引が逮捕されるのか。家族を守ろうとして行った犯行が、結局は自分が殺人犯人となり、殺人犯の母、り殺人犯の妹も悲しむ。やはり家族は崩壊する。身も蓋もない暗いラストになるのか。 櫛引の意外な不注意が破綻を招く。血圧計を忘れるなんて。重要な証拠となるコード類を砂浜に埋めるなんて。ロッカーの鍵を女友達の絵の具のチューブに入れるなんて(これは不注意の結果ではないが)。それまでの櫛引の周到な計画からは考えられないボンヘッドだ。第一の犯行の目撃者に恐喝され、彼をすぐ第二の犯行被害者にしてしまうのも安易な展開だと思うが。 練りに練った殺人方法が2つ。作者はあとがきで、「作中における殺人方法はほぼ確実に失敗します。間違っても模倣などされませんよう、お願いします」と書いている。あれ以外にもいろいろな殺人方法が紹介される。いくつかは自分にもできそうだなと思えるものもある。危険だな。 |
| 2008年5月5日(月) 「黒い家」(貴志祐介・著)を読む ミステリーというよりホラーだった |
| 97年第4回日本ホラー大賞受賞作でありベストセラー。99年には森田芳光監督、大竹しのぶの主演で映画化。大竹の怪演ぶりが評判を呼び、しつこいぐらいラストは怖かったという。そして今年は韓国でリメークされた。すでに先月公開されたようだが県内では今のところ公開なし。結局映画はどちらも見ていない。余談だが、明石家さんまが、「こんな映画なんかちっとも怖くない、私はもっと怖い大竹しのぶを知ってる」、と言ったとか。 主人公・若槻は保険会社の支払い査定員である。ある日、顧客の家〜これが黒い家、悪臭漂う不気味な家なのだ〜に呼び出され、子どもの首吊り死体の第1発見者となってしまう。ほどなく死亡保険金が請求されるが、菰田夫婦の不審な態度・行動から他殺を信じて疑わない若槻は独自調査に乗り出す。それが恐怖の序章だった。信じられない悪夢は恋人・恵にも襲い掛かる。 作者の貴志祐介は朝日生命保険に勤務していたというだけあって、生命保険会社の内幕に詳しく、保険金詐欺などの実例は生々しい。毒入りカレー殺人事件など、保険金詐欺は枚挙にいとまがないほどが、病院などがグルになっている場合もあるという。保険金請求の半数は不正であるという人もいるようだ。 菰田重徳はたぶん保険金搾取のため故意に指を欠損させた。たぶん子どもを自殺に見せかけて殺した。たぶん両手首を裁断機で切り落としてしまった。しかしこれらはみな、たぶん妻・菰田幸子の差し金だった。このままいけば当然最後は命を狙われる。この小説で怖いのはオカルトでも心霊現象でもゾンビでもない。人間が怖いのだ。それも女だ。悪いのも怖いのも女なのだ。 「サイコパス」とは心理学用語で言うところの背徳症候群や反社会性人格障害といった精神的情緒欠如者のこと。自分の欲望を満たすためなら人を殺すこともためらわない、人間らしい心、他人に対する思いやりとか優しさとかいった感情が生まれつき欠落している人間のことを指している。自分の子供にさえ愛情を抱くことのないサイコパス、情性欠如者が生命保険システムと結びついたとき、自分にとって身近な人間の存在は金をもたらす特別な意味を持つ存在へと変貌する。 刃物を持ったって相手は女1人。若槻の恐怖、及び読者が感じる恐怖の異常さは作者の筆の力によるものなのだろう。 |
Hama'sPageのトップへ My Favorite Mysteriesのトップへ