| 2019年2月2日(土) 「白夜」(東野圭吾・著)を読む |
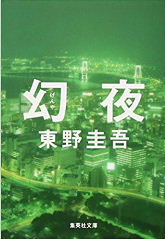 文庫本で779ページある。1日に100ページずつ読み続け、ほぼ1週間で読み終えた。何年か前に読んだ「白夜行」の続編のようでもある。小説の世界観が似ているが、単独の長編として読んでも違和感はない。 文庫本で779ページある。1日に100ページずつ読み続け、ほぼ1週間で読み終えた。何年か前に読んだ「白夜行」の続編のようでもある。小説の世界観が似ているが、単独の長編として読んでも違和感はない。阪神淡路大震災から物語は始まる。その混乱のまっただ中で、衝動的に殺人を犯してしまった男。それを目撃していた女。二人は手を組み、東京に出ていく。女は、野心を実現するためには手段を選ばない。男は、女を深く愛するがゆえに、彼女の指示のまま、悪事に手を染めていく。やがて成功を極めた女の、思いもかけない真の姿が浮かびあがってくる。彼女はいったい何者なのか――謎が謎を呼び、伏線に伏線が絡む。 とまあ、帯に書いてはあるが、帯以上に読み手にワクワク感を抱かせる。長いのは敬遠される傾向にあるが、面白い物は面白い。長さは関係ない。寝る前の1時間ほどで毎晩100ページほど読み進めるが、次の日のことを考えなければずっと読んでいたい。東野圭吾のストーリーテラーとしてのたぐいまれなる能力に打ちのめされる。 不満はラストに欲求不満になること。刑事と男のラストがあっさりとし過ぎ。美冬は最大の協力者を失い、どうやって生きていくのか。つまり「白夜行」、「幻夜」と来て、さらなる続編があるのか。「夜」の三部作とか。 |
| 2014年11月7日(金) 「パラドックス13」(東野圭吾・著)を読む |
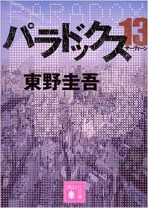 「すべてがFになる」の森博嗣は理系作家で、東野圭吾は文系作家だと思っていた。しかし、この小説を読むと東野圭吾の理系ぶりも生半可なものじゃないなと分かる。 「すべてがFになる」の森博嗣は理系作家で、東野圭吾は文系作家だと思っていた。しかし、この小説を読むと東野圭吾の理系ぶりも生半可なものじゃないなと分かる。13時13分13秒に東京から人間が消えた。残っていたのは13人だけ。13人が次々と襲い掛かる天変地異や悪性インフルエンザと戦いながらのサバイバル・ゲーム。異常時には正も悪もない。生き延びる術(すべ)が正なのだろう。東野圭吾には珍しいSFモノである。 13時13分13秒から13秒間に起こったのがP3現象だ。この現象の間は時間の連続性に変化が起こる。つまり13秒間だけ時間が縮む。その間を普通に過ごした人間には何の影響もないが、その13秒間に死んだ人間がパラレルワールドで復活するのだ。 1次元(直線だけ)の世界では2次元の広がりは奇跡である。2次元(平面)の世界の人間は3次元の高さは想像でしかない。同様に3次元(立体)の世界から4次元の世界を体験することは不可能だ。しかし、3次元から2次元は簡単に見ることができるし、2次元から見る1次元も不思議でもなんでもない。 0次元は点である。1次元は線。1次元の切り口が0次元となる。2次元を切ると切り口は線、つまり1次元である。3次元の立体を切るとその切り口は2次元の平面だ。同様に4次元を切るとその切り口は3次元。つまり我々は4次元の切り口に住んでいるのだろう。 0次元は点でしかないが、1次元は線、つまり0次元が並行移動してできた長さとなる。2次元は1次元が並行移動し、縦×横、つまり平面となる。3次元は平面が並行移動し高さが加わる。縦×横×高さ。じゃあ4次元は3次元が並行移動したもの、縦×横×高さに何が加わるのか。時間である。縦×横×高さ×時間、これが4次元と考えれば、P3現象なるものも説明がつくのだろう。 面白くて読むのがやめられなくなる小説である。地震、津波に超大型台風らしき暴風雨、街は原型をとどめない。いたるところに陥没や地割れが発生し、移動さえもままならない。病人は出るし、足手まといの老人や幼児、子どももいる。途中から得体の知れないヤクザも加わり、チームワークも乱れる。食料もじき尽きるだろう。都心を現場とする13人のサバイバル・ゲームだ。 そしてラストは?消えた他の人間はどこに行った? 東野圭吾の力作であり、力技で想像不能な世界を描く。まったく荒唐無稽な凡作にならない所が彼の手練である。ラストが納得できるかどうか、また論理の破たんはないのか、物理学者でない我々には分からないが、SF小説として読むと十分に楽しめる作品である。 |
| 2014年3月5日(水) また雪だあ 「11文字の殺人」(東野圭吾・著)を読む |
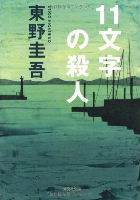 数日前、東野圭吾の「11文字の殺人」を読んだ。「無人島から殺意を込めて」から改題した題名だという。11文字とはつまり「無人島から殺意を込めて」。編集者の意向で改題されたというが、まあ駆け出しのころの東野圭吾だから仕方がないが、「無人島から殺意を込めて」の方がよかったと思う。 数日前、東野圭吾の「11文字の殺人」を読んだ。「無人島から殺意を込めて」から改題した題名だという。11文字とはつまり「無人島から殺意を込めて」。編集者の意向で改題されたというが、まあ駆け出しのころの東野圭吾だから仕方がないが、「無人島から殺意を込めて」の方がよかったと思う。後半に、外部と接触を断たれた無人島での犯人捜しは、いわゆるクローズド・サークル(吹雪の山荘ものともいう)だ。私の好きなパターンである。それを思わせる「無人島から〜」の方が期待感が大きい。 1987年カッパノベルズ(光文社)刊とあるから、バブル経済が始まったばかりの頃である。ちなみにバブル景気とは1986年12月から1991年2月までの51ヶ月間を言う。ストーリー的にそんなバブル時代を思わせる展開もある。独身の女性が豪華なマンションに住み、バーでカッコいい男性と出会い交際が始まる。昔のトレンディドラマの流れである。そう言えば、「11文字の殺人」も2時間ドラマ化されたミステリーだという。 「狙われている」とおびえていた恋人が殺され、彼の遺品の中から大切な何かが盗まれた。女流推理作家の主人公とやはり女性の編集者が真相を負う。そして関係者全員と共に舞台を無人島に移し、「犯人は〜です」、を期待するのだが。。 意外な真犯人もなんとなく意外でなくなる中盤、ストーリー的にゆるく、キレがなくなる。東野の作品の中でも最近の作品と比較したら面白さ的に中の下であろう。内容より、宮部みゆきが書いている解説−ガッツあふれる体育会系作家−の方が面白い。文庫化のための特別に執筆した解説であり、東野圭吾論みたいなものを奔放に書いたようなあとがき。「11文字の殺人」の内容にはほとんど触れていないのも分かるような気がする。 |
| 2013年9月6日(金) 「マスカレード・ホテル」(東野圭吾・著)の感想 |
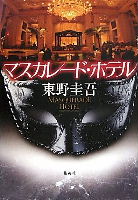 題名の「マスカレード・ホテル」はホテル名ではない。「マスカレード」とは「見せかけ、虚構」、あるいは「仮面舞踏会」の意味である。昔、安全地帯が歌った「マスカレード」。歌詞検索で見ると、「あなたは嘘つきな薔薇」というフレーズがある。マスカレードとは「見せかけ、虚構」であることが分かる。 題名の「マスカレード・ホテル」はホテル名ではない。「マスカレード」とは「見せかけ、虚構」、あるいは「仮面舞踏会」の意味である。昔、安全地帯が歌った「マスカレード」。歌詞検索で見ると、「あなたは嘘つきな薔薇」というフレーズがある。マスカレードとは「見せかけ、虚構」であることが分かる。東京都内で発生した3件の連続殺人事件。現場に残された数字を解読すると次の殺人は、超一流ホテル・コルテシア東京が現場になりそうだ。捜査員が何人かホテルスタッフとして潜入する。フロントクラークとして潜入したのが警視庁捜査一課の新田浩介だ。立場上新田を指導するのが優秀なフロントクラーク山岸尚美である。 ホテルには様々な人間がやってくる。山岸はおもてなしの心で精いっぱいの対応をする。クレームにも柔軟に対応する。お客様を満足させるのが第一という姿勢を貫く。 それに対して刑事の新田はどんな客にでも容疑者を見るような鋭い視線を投げかける。刑事ならではの目、勘で尚美にも見抜けなかった客の秘密を見抜いたりする。 それぞれがプロとしての仕事ぶりはパーフェクトであるが、2人は反目することも多かった。不審な客に対して2人の違う対応がおもしろい。結局、事件とは関係なかった。そんな風にそれぞれの章が終わるのだが、ラストに行くと関係ないどころか繋がってくる人物もいるから注意が必要だ。 そして犯人のターゲットとは?これが一番の思いがけない人物だった。もちろん犯人も。さすが、東野圭吾。推理小説としてきちんと押さえるところは押さえる。しかし動機が不満だ。そんなことで、と思う動機である。なぜこの高級ホテルなのかも動機にからんでくる。 |
| 2012年4月9日(月) 「夜明けの街で」(東野圭吾・著)を読む |
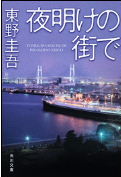 「東野圭吾の新境地にして最高傑作」、だという。確かに新境地であるが。。 「東野圭吾の新境地にして最高傑作」、だという。確かに新境地であるが。。「不倫する奴なんて馬鹿だと思っていた。ところが僕はその台詞を自分に対して発しなければならなくなる」。 結局は女に利用されただけか。修羅場もなくハッピーエンドかい。主人公の渡部がいい思いをしただけ、もとのさやに収まり、めでたしめでたし。くだらないし、つまらん。ただし妻が不倫に気付いていた節もある。あいまいな記述だが。 ライトノベル的不倫モノに、ミステリーはほんの付けたしだった。東野圭吾の新境地は失敗作だったと思う。渡部淳一の不倫モノだとしたら楽しく読めたかも。東野圭吾のミステリーだと思うから別の展開を期待したのだ。 そもそもミステリーと恋愛の融合は成り立たないなんて、誰か言ってなかったか?ヴァン・ダインの二十則にあったような。 新境地は新境地だが、最高傑作とは読者をバカにしている。最高傑作かどうかは読者が決めるもの。出版社が煽ってどうする。だまされた。 |
| 2012年2月14日(火) 先日読んだ「新参者」(東野圭吾・著)の感想 |
| 加賀恭一郎シリーズ。「このミス2010年版」、「週刊文春ミステリー」ダブル1位に輝いたという。先日は映画、「麒麟の翼〜劇場版新参者〜」を観て泣いた。俳優・阿部寛は加賀恭一郎役がすっかり板についた。この小説でも加賀を阿部寛のイメージで読み進める。個人的にはガリレオシリーズの福山雅治よりイメージに合う。 新参者、日本橋署の加賀が担当するのは小伝馬町の女性殺人事件だ。章ごとに被害者や関係者、凶器に繋がる玩具などを小出しに登場させる。舞台は下町情緒の漂う人形町界隈だ。 第1章は「煎餅屋の娘」。神出鬼没、加賀は煎餅屋に現れる。空白の30分間、アリバイ崩し、上着を着ていたか脱いでいたかなど、短編ミステリーに下町の風情と人情を絡ませる。第1章だけでも推理小説としてまあまあの作品に仕上がってるではないか。 しかし、物語は続く。第2章は「料亭の小僧」、第3章「瀬戸物屋の嫁」、第4章「時計屋の犬」、第5章「洋菓子屋の店員」、第6章「翻訳家の女」、第7章「清掃車の社長」、第8章「民芸品屋の客」、そして解決編とも言えるのが第9章の「日本橋の刑事」となる。 しかし、それぞれの章が繋がり全体として1つのミステリーとなるが、残念、盛り上がりに欠ける。犯人も思いがけない犯人ではない。動機も弱い。トリックも特にない。これがミステリーかと言えば、不足があろう。「このミス」も「週刊文春」も早まったな。 |
| 2009年9月24日(木) 「さまよう刃」を読む せつないね |
| やりきれない想いで読んだ。娘を持つ親としては切ない本だ。読み始めて数ページでグイグイと引き込まれる。主人公長峰に思いっきり感情移入。殺せ、ぶっ殺せ!少年法に委ねたら長峰の気持ちは少しも収まらない。自分の手で復讐するんだ。殺された娘のかたきを取るのだ! 主人公長峰の妻は5年前に病死した。今はそれでも、高校1年生の一人娘・絵摩と幸せに暮らす。花火大会の夜、友人たちと出かけた絵摩だが、いつまで待っても帰って来ない。ケータイは電源を切られた。居ても立ってもいられない長峰。 2日後荒川の下流で絵摩の死体が発見された。未成年の少年グループによる蹂躙の末の遺棄だった。密告電話によって犯人を知った長峰はアジトになっているアパートを突き止める。部屋にはビデオテープが散乱していた。ビデオレコーダーに挿入されていたビデオを再生すると、なんと絵摩が少年たちにレイプされるシーンが写っていた。激昂する長峰があわれだ。 復讐の鬼と化した長峰はグループの少年1人を殺し、被害者の親だったが加害者、容疑者にもなった。絵摩をレイプしたもう1人の少年を追いながら、自らも警察から逃走する。少年が逮捕される前に殺すのだ。少年は逮捕されても少年法で保護される。警察は長峰を全国指名手配で捜索する。 長峰の協力者・和佳子が現れる。なぞの密告電話の主は誰なのか。また、自殺していた別の少女も同じ少年らによってレイプされていたことが判明する。その映像を確認する父親の叫び声もいたたまれない。切ない。 この本は寺尾聰主演で映画化され10月10日に公開される。絶対に観よう。たぶん結末は変えるだろうな。原作の結末は賛否が分かれるだろうが、映画では果たしてどうなる。 長峰がもう1人の少年を殺して自首、もう1人の少年が長峰を殺して逮捕される、少年は保護され長峰は逮捕、少年は保護され長峰は猟銃で自殺、協力者・和佳子が少年の盾になり死ぬ、自殺した娘の父・鮎村が少年を殺す、など、結末はさまざまに考えられる。 映画では警察の立場をどう描くのだろうか。あくまで本来の公務を愚直に執行する警察か。刑事だって長峰の気持ちが十分に分かっている。復讐させてやりたいと思うだろう。本のラストでは警官一人がこの事件の後に辞職した。警察は正義の味方か、違うな。法律の番人か、違うな。警察は何なんだ。少年法に守られる少年は誰が裁くのだ。 ミステリーとしてとても面白かった。 読みごたえがあり深く考えさせられる小説だ。ラストはあれでいいのだろうか。ラストに密告者の正体が明かされるが、誰もが予想していた人物ではなかった。とってつけたようなミステリー色っぽい意外な密告者だったが、誰もが思う”あいつ”でも良かったと思う。その方が気持ち的に救われる。 |
| 2008年12月17日(水) 「聖女の救済」を読む トリックは虚数解 |
| おなじみガリレオシリーズ最新作。同シリーズ、映画「容疑者Xの献身」が福山雅治、柴咲コウ主演で現在大ヒット公開中だ。ガリレオシリーズではないが、やはり東野圭吾の作品「流星の絆」もテレビ放映中、いよいよ終盤にさしかかる。本、映画、テレビと、東野圭吾の勢いと人気はとどまるところを知らない。もちろん僕も東野のファンの一人。「容疑者Xの献身」も「流星の絆」も読んだ。映画も観た。 さて、この「聖女の救済」の毒殺トリックは超難解だ。東京で男が毒殺されるが、容疑者の女性は札幌にいた。もちろん鉄壁のアリバイがある。いかにして被害者だけ(一緒にコーヒーを飲んでいた女性もいるのに)をピンポイントで毒殺できたのか。東野圭吾、渾身の新トリック登場というところか。 ガリレオこと湯川が言う、「おそらく君たちは負ける。僕も勝てない。これは完全犯罪だ」と。そして湯川が推理した真相は虚数解。まさか。天才物理学者、湯川が、普通の女性が考え出したトリックを暴けないというのか。この女性の描き方が実にいい。才色兼備、冷静沈着、まさに「聖女」だ。 だからと言って草薙刑事が容疑者に恋をするか。余計な展開だ。「容疑者Xの献身」の数学教師じゃないのだ。捜査する側の刑事が容疑者への余計な感情は推理小説にはご法度なはず。邪魔になるだけだ。東野圭吾もつい筆がすべったと思われるところが何箇所かあった。 それでも、相変わらず、サクサクと読みやすいミステリーだ。読み出したらやめられない面白さである。しかし、あのトリックが実際に可能か。そんなにうまくいくはずがない。推理小説のトリックに文句を言う筋合いではないが、ついそう思うようなトリックだった。しかしまあ、純粋に楽しめればいいのだ。 内海がアイポッドで福山雅治のアルバムを聴く。楽屋落ちであるが、ニヤリ。湯川と草薙の対話も随所にユーモアが感じられ、何度も笑った。 |