| 2014年5月5日(月) 予告殺人(アガサ・クリスティー・著)を読む 洋モノは疲れる |
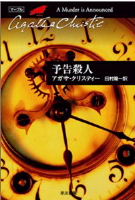 名前を覚えるのがやっかいだ。ファーストネームで呼んだり、ファミリーネームで表記されたり、はたまた愛称で呼んだりする。そのたびにこの名前は誰?と登場人物一覧を開き直す。 名前を覚えるのがやっかいだ。ファーストネームで呼んだり、ファミリーネームで表記されたり、はたまた愛称で呼んだりする。そのたびにこの名前は誰?と登場人物一覧を開き直す。レテシィア・ブラックロックは愛称ブラッキーに、レェティ、そしていつのまにロティ?なんでロティなのだ。翻訳家が間違ったのか。いや、実はこれは伏線だった。しかも双子だったとは(完全なネタバレ、ごめん)、何とかの十戒に、トリックに双子を使っちゃならん、なんてなかった? ジェーン・マープルは探偵好きな老婦人。安楽椅子に座り編み物をする小柄で少し太った婦人。ぼけることもなく、頭脳明晰なおばあさん、これは作者のアガサ・クリスティに繋がりそうだ。 |
| 2004年7月22日(木) 「ABC殺人事件」(アガサ・クリスティ・作 中村能三・訳) |
| エルキュール・ポワロのもとにABCから挑戦的な手紙が届く。挑戦状の予告どおりに、アンドーバーでアリス・アッシャー婦人が殺される(A、A・A)。さらに第2の手紙のとおりに、ベクスヒルでベティ・バーナードが殺される(B、B・B)。3人目の被害者はチャーストンで殺されたカーマイクル・クラーク卿だ(C、C・C)。そして死体のそばにはABC列車時刻表がその地名のページが開かれたまま置かれている。やがて怪しい人物が登場する。果たして4人目は。。 お馴染み、アガサクリスティ推理小説の、古典中の古典である。怪しすぎるカスト氏の行動に誰もが彼を犯人と思う?いや、違う、その逆だ。絶対に彼を犯人とは考えない。推理小説を読み慣れない人だってそう思うに決まっている。逮捕され、「殺したかも知れない」と自白もしたカスト氏であるが、じゃあ動機は?ポアロに挑戦した理由は?そう考えると彼が犯人であるはずがないのだ。 ある順番により無差別に殺人を繰り返す犯人は、実はその中の一人だけを殺したかったはず。犯人像をカバーし、事件を混乱させるために他の人間をある一定の法則にのっとり殺していく。ポアロへの挑戦状だって捜査を混乱させるものだろう。これは読んでいて当然考えつく推理である。だが私の能力ではせいぜいそこまで。犯人像へはそれ以上一歩も近づけない。しかしさすがはポアロ。ラストでは切れ味鋭いポワロの推理に酔いしれる。 エルキュールは英語読みではヘラクレスだった。蛇足である。ヘラクレスという読みは事件の解決に何のヒントにもならない。念のため。 |
| 2001年11月7日(水) 「そして誰もいなくなった」(アガサ・クリスティ・著 清水 俊二・訳) |
| 推理小説の古典とでも言うべき、アガサ・クリスティの名作である。中学時代に学習雑誌の付録で読んだ。文庫本を買ってもう一度読んだのはそれから10年ほど経ってからだったと思う。有名なマザーグース童謡・「10人のインディアン」通りに人間が殺されていく小説だ。2度読んだことのある推理小説であるが、殺人犯はいったい誰で、その方法はなど、すっかり忘れてしまっている。 3度目を読むきっかけになったのは、たまたま本屋で見つけた、夏樹静子の「そして誰かいなくなった」という文庫本である。なんだ、この人を食った題名は。初めはアガサ・クリスティのパロディかと思った。が、そうでもなく本格的な推理小説らしい。じゃ、読んでみよう。いや、待てよ、その前に、もう一度、アガサ・クリスティの本家・本元を読んでからにしようじゃないか、というわけだ。 3度目の「そして誰もいなくなった」であるが、いや〜、おもしろかった。犯人は10人のうちの1人であることはわかっていた。しかし、だれだったけ?最後に生き残る人物が犯人だと思うのだが、最後の一人も童謡どおりに首をくくって死んでしまうはずだ。トリックを解明するボトル・レターまで早くたどり着きたい。ノートに、人物と殺され方、マザー・グースとの一致点、過去の法律で裁かれない犯罪など?を記入しながら読み進んでいく。インディアン島での殺人事件は言わば密室殺人である。作者は、意図的かどうかわからないが、読者に手がかりをあまり与えていない。読者と作者の真剣勝負なんてものじゃない。解明不可能な殺人トリックを最後に解き明かして、読者を悔しがらせて、ほくそえんでいる作者。ラストのトリック解明では作者の勝ち誇りが感じられる小説である。 ところで、翻訳者の清水俊二って、映画のラストで、字幕翻訳者の名前で、時々見る名前じゃない? |
| 2001年12月29日(土) 「アクロイド殺人事件」 |
| 本格ミステリーの古典的名作(1926年に発表された)の一つである。西村京太郎のミステリーに読みなれると昔の名作は読むのに疲れる。一気に読んでしまわないと伏線も伏線でなくなってしまう。カタカナの登場人物が誰だったのか、いちいち扉の登場人物一覧に戻りながら読み進める。疲れを我慢しながら読んでいく。やっとアクロイド氏が殺され、怪しい人間が様々に浮かび上がっていくあたりからアガサ・クリスティのわなにずんずんはまっていく。 世界的に有名な作品である。当然、最後にあっと言う意外なラストが待っているのだろう。早くラストまでたどり着きたい。だが、犯人はポワロ氏のからまつ荘に集まった6人の中にいるということだ。だったらそれほど意外性のあるラストは期待できないじゃないか。せいぜい一番怪しかったラルフ・ペイトンが犯人ではないというぐらいか。あとは誰が犯人だって驚くほどのもんじゃないな。でもそれじゃ、本格的ミステリーの最後にしては味気ないものになってしまう。いったいどんな意外性が待っているのか。。 そしていよいよ結末。名探偵ポワロの、「つまり、それは、○○です!」の台詞で一気に疲れがぶっ飛んだ。これこそ推理小説の醍醐味だ。まさしく意外性以外なにものでもない。当時の推理小説家はもう2度とこの手は使えないと悔しがったであろう。まったくもって、やられた!である。 |