| 2018年2月14日(水) 「人間じゃない」(綾辻行人・著)を読む |
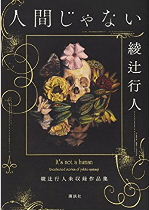 綾辻行人の単行本未収録となっていた短編を集めた作品集。古いものは93年からのものであり、最新は2016年とかなり幅広い。後日談として発表されたものが多いので、単体として読み応えのある本格短編集とはなっていないが、中編の「洗礼」は楽屋落ち的本格犯人当て趣向だったり、ラストの「人間じゃない」は、もともと漫画で絵でしか出来ないある仕掛けがあったものを小説化したものであったりと、内容はホラーも含めた変化球ミステリー。読みやすく、寝転がっても読める、久しぶりに読んだ綾辻行人だった。 綾辻行人の単行本未収録となっていた短編を集めた作品集。古いものは93年からのものであり、最新は2016年とかなり幅広い。後日談として発表されたものが多いので、単体として読み応えのある本格短編集とはなっていないが、中編の「洗礼」は楽屋落ち的本格犯人当て趣向だったり、ラストの「人間じゃない」は、もともと漫画で絵でしか出来ないある仕掛けがあったものを小説化したものであったりと、内容はホラーも含めた変化球ミステリー。読みやすく、寝転がっても読める、久しぶりに読んだ綾辻行人だった。 |
| 2013年2月5日(火) 「びっくり館の殺人」(綾辻行人・著)を読む |
| 「かつて子どもだったあなたと少年少女のためのミステリーランドシリーズ」第9回配本作品だという。平易で読みやすい文体に、漢字にはルビがふってある。 びっくり館で起こる殺人事件は1件だけ。トリックは密室殺人のみ。しかし、「七色のびっくり箱を抜け出し隣の部屋に通じる秘密の抜け穴があった」、なんてドン引き、ふざけた謎解きに失望させ、実は、密室の中のある物が殺人者だったと主人公が推理して、トリックの解明は終わり。ミステリーとして物足りなさが過ぎる! びっくり館の住人である古屋敷龍平。被害者はその古屋敷氏だ。その孫だと思っていたひ弱な少年がトシオ。しかし、古屋敷老人の腹話術で語られる禁断の秘密とは。 おいおい、これは少年少女向けのミステリーだぞ。なんと、トシオとリリカの姉弟の父親は古屋敷龍平だった?リリカは母親から悪魔の子と呼ばれ、リリカは母親に殺された、など、古屋敷の腹話術でおどろおどろしく語られる。だったら、古屋敷老人を殺した犯人はすぐに分かる。動機も分かる。テーマは児童虐待。 綾辻行人の作品は久しぶり。それも夢中になって読んだ館シリーズの8作目だというのでこの本もかなり入れ込んで読んだ。もちろん謎の建築家、中村青司による設計の館だ。文中には、「迷路館の殺人」も出て来るし、「迷路館の殺人」に登場する探偵、鹿谷門実も登場する。しかし、中村青司も鹿谷門実もこの本では存在が意味不明。中途半端な登場でしかない。 「館」シリーズとして期待して読むと肩透かしをくう。「びっくり館」というより、「がっかり館」という人がいた。それでも、ベストセラー作家、私も好きな道尾秀介氏はこの本を絶賛しているというが、本の評価とは分からないものだね。外交辞令ならぬ対談辞令であろう。 |
| 2010年3月2日(火) 「Another(アナザー)」(綾辻行人・著)を読む ハードカバーで678ページ |
| 久しぶりに読んだ綾辻行人の本。「暗黒館の殺人」以来3年ぶりの新作だという。力作である。「暗黒館の殺人」は上・下巻あり読むのがいやになるくらい長かったが、この「Another」も単巻だが長い、というよりぶ厚い。しかし、中学生の一人称による語り口で物語が進むだけあって言い回し等が平易であり、サクサクと読み易い。会話主体のページが多く、行間に隙間も多い。 内容はホラー+ミステリー。表紙の絵が、横積みされる本屋でもひときわ異彩を放つ。ホラー小説だと訴えかけてくる存在感がある。少女の顔は背表紙にもつながりもう1つの目が背表紙に描かれる。机の上の置くと背表紙の角度によって顔がいびつになり、ますます怖くなる。双眸をまともに見れなくなる。それほど怖い表紙だ。 6ページまでのイントロダクションがホラーのショートショートになっている。最後の数行に読者は震え上がる。クラス全体が善意で行ったあることが26年間にも及ぶ恐怖の始まりだった。トイレの花子さんのようの学校に伝わる罪のない怪談話ではない。口裂け女のようにたわいない都市伝説でもない。とにかく人が死ぬのだ。こんなに人が死ぬ小説も珍しい。それも学校で、3年3組に限ってほとんど毎年7、8人も。生徒や生徒の親兄弟が次々に殺されたり、事故死や病死だったり、自殺だったり。 東京の私立中学から地方の公立中学校(夜見山北中)に転向してきた榊原恒一が物語を語る。彼には同じクラスの少女、ミサキが見えているし話もするが、他の友人たちには見えないらしい。不思議な行動をとるミサキ。彼女は実体のない幽霊なのか。あるいは榊原に死人が見えるなどの特殊能力があるのか。 全体はパート1とパート2に分かれる。パート1のラストでも張り巡らされた伏線が繋がり、得体の知れない少女ミサキの正体が分かり、そうだったのかと、ホラーなのにミステリー解決編の趣がある。 ミステリーの要素はパート2でさらに増幅される。誰がAnother、つまりもう1人(実は死者)だったのか。647ページで分かるその人に声を挙げる。あてずっぽうで多分この人物かと思う人もいるだろうが、半分は当たっても、実は〜ということまで推理できる人はいないだろう。実は〜、これはビッグサプライズであった。ミステリーを読む醍醐味である。 見方によっては作者はアンフェアである、ミステリー作法においてルール違反ではないかと思う人もいるだろう。しかしこれもジャンルとして確立されている叙述トリック(作者が読者をペテンにかける)なのだ。賛否両論がありそうだと思ったが、ネットでレビューなどを読んでいてもそれに触れる人は少ないようだ。あるいは最後のビッグなサプライズを堪能したということか。 3年3組になぜ死者がまぎれ込み、そのため毎年多くの死人が出るのはどのような科学的根拠に基づくものか、それは解明されない。この部分は完全にホラーファンタジーの世界である。その死者が誰であるのか、その死の連鎖を止めるためにどうすればいいか、自分の母親が死んだこととのつながり等、ミステリーとしてかなり面白く読めた。 最後の章はOutroduction。なるほど Intoroductionがあれば、Outroductionもあるのか。序章に対して終章=Outroductionということか。初めてこの言葉(造語なのか)を知った。 |
| 2008年6月24日(火) 「殺人方程式」(綾辻行人・著)を読む あの物理トリックには仰天 |
| 間違って削除してしまいました。 |
| 2006年7月26日(水) 「暗黒館の殺人」(上・下)を読む 綾辻行人のファンだから読んだが、長すぎ! |
| 上巻654ページ、下巻639ページ。新書版2段組で、かなりぶ厚い本、2冊。よほど気合を入れないと読み出せない長さである。購入してしばらく積ドク状態だったが、何冊かまとめ買いしてあるミステリーを全部読んでしまい、仕方なく(意を決して)読み始めたのは、ほぼ1ヶ月前。上巻の3分の2ぐらい、400ページを超えたあたりでやっと1人殺されるが、そこまでは順調に読めた。しかし、その後から時間がかかった。謎解きよりホラーかと思える展開に戸惑ってしまった。いつもの「館シリーズ」に、もう1つの「囁きシリーズ」がミックスしたような内容になる。 それでもコテコテの古典的推理小説。長いと言っても斜め読みするわけにもいかない。何度も挫折しそうになりながら、約1300ページ、とりあえず読み終えた。「黒猫館の殺人」以来、約14年ぶりの館シリーズの集大成、綾辻行人、渾身の力作である。 例によって館の平面図が挿入されているが、暗黒館は、東館、西館、北館、南館の4館から成り、平面図は2つ折りで4ページ、2枚が折込まれている。当然、あっちを見たりこっちを見たりしながら読むことになる。さらに部屋に秘密の通路があったりするから、必要に応じて途中にもさらに図面が挿入される。 登場人物がすごい。主な登場人物として冒頭に紹介される人間は29人。人数も多いが、キャラがまたすごい。まあ、なんと畸形や病気や、異常な人間が多いことか。早期老化症の子ども(略してソウロウ症、10歳ぐらいでもう老人)、シャム双生児の美人姉妹(H型二重体、腰のところが繋がっている)、黒いフードをすっぽりかぶり性別不明の老人、足の指が3本の男(欠趾症あるいは合趾症)、せむし(くる病)の玄関番、自分の娘と、さらに孫娘との近親相姦の絶倫老人、100年以上地下の檻で生き続ける謎の不老不死老人、知的障害のある子ども、精神疾患の女、白内障の男、びっくりしたままでいる(?)母親、生まれてすぐ座敷牢に閉じ込められたままの男、記憶喪失症の男2人、などなど。 そして、ダリアの日の、あの<宴>。ウエ〜!心臓の形をしたデカンターに赤葡萄酒のような酒、赤黒いドロドロスープ、中には肉のような具が溶け込んでいた。「食したまえ、肉を」。気持ち悪くて、もうビーフシチューやキムチ鍋が食べられなくなる! 下巻に時間がかかったが、何が何でもラストまで読んでやる!解決編を読んで”驚愕のラスト、大どんでん返し”を堪能しよう。その意地で読み続けたが、何しろ、およそ1ヶ月にも及ぶ細切れ読書。つじつまを合わせようにも、関係ある部分を読み返すのに骨が折れる。どのあたりだったか探すのが大変なのだ。 結局、何が何だか分からないまま、消化不良、欲求不満のまま読了。教科書体活字を使っている独白部分が誰の独白だったのか分かったか?時には「私」が主語の一人称小説。おや、今度の主語は「僕」か。主語を使い分けるのはもちろん人物が違うから?2人の視点の他に、「視点」が浮遊して時々、客観描写になる。さらに時間の概念に注意して読もう。視点がバック・トゥ・ザ・フューチャー&パスト。現在、18年前、27年前がいっしょくたんにミスリードされる。折原一の作品のように、AがBであり、BがAだった、しかし実は。いやはやラストまで読んでこんなにワケの分からない(納得できない)小説もあまりない。 綾辻行人の作品をを読みその世界にどっぷりと浸る、途中経過を楽しむ、ファンならではのそんな読み方、楽しみ方で良しとしよう。綾辻のファン以外、あまりお薦めできません。 |
| 2003年11月24日(月) 「緋色の囁き」(綾辻行人・著) ホラー系ミステリー |
| かなり前(二十数年も前)、イタリア製ホラー映画「サスペリア」を観た。原色、特に赤を強調した色彩&映像と、ゴブリンというグループが演奏していた音楽(サーカムサウンドとか言っていた)が、観る者に効果的に恐怖感を植え付け、大ヒットした映画である。もちろん私も観た。内容は音楽学校の女子寮で起こる凄惨な殺人事件やオカルト的現象?がメインだったと思う。 綾辻行人の「緋色の囁き」は、本文でも後書きでも触れているが、まさにその「サスペリア」を彷彿とさせるミステリーである。「館」シリーズではなく「囁き」シリーズの一冊であるが、聖真女学園高等学校の聖真寮を舞台とする「館」シリーズと言ってもいいような内容である。 西洋の魔女伝説を現代の女子高校生の連続殺人事件に絡ませる。聖真女学園(セイシンジョガクエン)はセイ・マジョガクエンとも読める。意外な犯人を推理する楽しみと共に、人間の深層心理に潜在する狂気を綾辻独特の文体でユラユラと?味わうことができる。 綾辻行人は最近、ここ5、6年か、まったく新作を発表していない。新しい「館」シリーズを執筆中という噂もあるが、長編はおろか短編(新作)も書店で見ることが全くなくなった。氏の主な長編はほとんど読んだと思うが、古典的ゴチック推理小説を書く人は極端に少ない現在、彼が新作を発表しないというのは淋しい。まだ若いのに、もう筆を折ってしまったのだろうか。 |
Hama'sPageのトップへ My Favorite Mysteriesのトップへ