| 2013年4月6日(土) 「裁判員法廷」(芦辺拓・著)を読む |
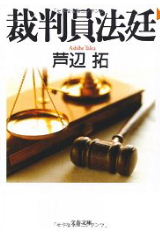 2009年施行の「裁判員制度」をとりあげた、おそらく本邦初の小説集(著者の言)。どこの誰でもなりうる裁判員である。自分にもいつ裁判所から呼び出し状が来るかも知れない。もし来たら受け入れざるを得ないのだろうか。仕事もあるし、できれば来ないでほしい。 2009年施行の「裁判員制度」をとりあげた、おそらく本邦初の小説集(著者の言)。どこの誰でもなりうる裁判員である。自分にもいつ裁判所から呼び出し状が来るかも知れない。もし来たら受け入れざるを得ないのだろうか。仕事もあるし、できれば来ないでほしい。そもそも、全くの素人が裁判で被告人の量刑を決めたり、有罪や無罪を主張したり、弁護人や検察に意見を述べるなど、そんなことできるのか。もし自分が被告人なら、ずぶの素人の裁判員なんかに裁判を受けたくないと、誰でもそう思うだろう。 本書は三つの中篇から成る。それぞれ別の事件を扱いながらも、裁判員や検察、弁護人は同一人物であり、取り上げられる裁判の段階が手続き順に配列されている、読了すれば、公判のおおよその流れが理解できるようだ。これから裁判員に指名されるかもしれない人にとっては参考になるだろう。 法廷にて裁判員たちは、弁護士の森江春策、検事の菊園綾子や証人たちの質疑応答を聞いていく。実際にそんな場面に裁判員として立ち会ったら、裁判員は複雑で微妙な事件に頭を抱えるだろう。それでも小説の中では見事な推理をする者もいれば、有効な意見を述べる者もいる。あくまで小説の中だけだろう。一般人とは思われない推理や着眼、発言に、小説だからと覚めた目で見てしまう。 3つの事件は関連性がない。だから短編小説として読んでもいいのだが、小説としてあまり面白くない。ラストがあいまいだったり、結局、この被告人は本当に犯人なのか冤罪なのか。読後にすっきり感がない。山も谷もないから、読んでいて疲れる。 裁判員制度を知るため、裁判員の仕事を知るためには、ただの解説書よりは本書を読んだ方が面白いのは確かだが、ミステリー的面白さを期待するとがっかりする。最後の「自白」はまあまあであるが。 |
Hama'sPageのトップへ My Favorite Mysteriesのトップへ