| 2013年7月29日(月) 「天啓の殺意」(中町信・著)を読む |
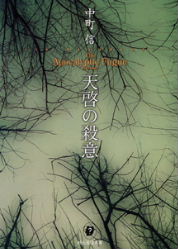 中町信というミステリー作家をつい最近まで知らなかった。新人?いや違う。1935群馬県生まれ、早稲田大学卒、2009年に逝去している。叙述トリックを得意とし、先日読んだ「模倣の殺意」など、大掛かりなトリックで読者を驚かせる作家だという。 中町信というミステリー作家をつい最近まで知らなかった。新人?いや違う。1935群馬県生まれ、早稲田大学卒、2009年に逝去している。叙述トリックを得意とし、先日読んだ「模倣の殺意」など、大掛かりなトリックで読者を驚かせる作家だという。「読者にしかける功名な罠」、「読後、呆然。あなたはこの真相に驚愕する!」など文庫本・帯に記載されるフレーズは十分に刺激的で、”読欲”をそそられる。”読欲”という言葉はあまり聞いたことがない。手元にある学研の現代新国語辞典にも載っていないが、食欲や性欲があるなら読欲があってもいいと思う。 6月17日に読んだのは「模倣の殺意」。叙述ミステリーとしてまあ、おもしろく読めた。読者をペテンにかける小説だった。 しかし、「天啓の殺意」は、中盤までは快調に読めたのに、終盤に疲れた。何がなんだか分からなくなる。いったいこの人物は、柳生照彦という推理小説作家の書いた登場人物なのか、中町信の小説の中の登場人物なのか。これはいわゆる劇中劇ならぬ、作中作だった。 柳生照彦という推理作家が実際の殺人事件を題材にした推理小説を書く。それに対し、タレント作家の尾道由紀子に解決編を書いてもらい、その後に自分の解決編を乗せるという、いわばリレー小説が作中に挿入される。小説の中の人物名は半年前の事件の人物と同じ名前であるからややこしくなる。 一気に読むべきミステリーである。数日の間隔を入れ、休み休み読んだのでは面白味が半減する。だから解決編のカタルシスもいまいちだった。思いがけない犯人は、本当に思いがけない、これは確かだ。中盤まで読んで、あてずっぽうでもこの犯人をいい当てるのは難しい。 さらに探偵役の人物。最初はほんの端役に過ぎない人物が終盤に突如として名探偵に変身するのだ。えっ!と思う。 中町信の作品は2冊読んだが、もういいかな、と思う。 |
| 2013年6月17日(月) 「模倣の殺意」(中町信・著)を読む |
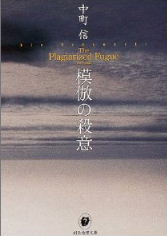 帯の「これはすごい!」とか、「騙されずに見破れますか」などと、煽られて平積みされている文庫本2冊を買った。犯人ではなく作者がトリックを仕掛ける叙述ミステリーのようだ。最初は最近の作品かと思って読み始めたが、時代が古い。帯をよく見ると40年前の作品だった。「40年前の傑作が今、再びの大ブレイク!」と書いてある。 帯の「これはすごい!」とか、「騙されずに見破れますか」などと、煽られて平積みされている文庫本2冊を買った。犯人ではなく作者がトリックを仕掛ける叙述ミステリーのようだ。最初は最近の作品かと思って読み始めたが、時代が古い。帯をよく見ると40年前の作品だった。「40年前の傑作が今、再びの大ブレイク!」と書いてある。坂井正夫という男が青酸カリによる服毒死を遂げた。しかし、坂井は殺されたのだと確信する2人の人物がいる。一人は中田秋子であり、もう一人は津久見伸助という男だ。 物語は2人の視線から交互に語られる、今ならよくあるパターン。2人が別個に行う調査や聞き込みから、全く別々の容疑者2人が浮かび上がる。遠賀野律子と柳沢邦夫だ。どちらにも動機はあり、どちらにもアリバイがあった。いったいどっちが犯人なのだ。 やがて、中田秋子と津久見伸助はそれぞれの人物のアリバイを見事に崩し始める。この辺りから不協和音が漂い始める。犯人が別々に2人いるのはおかしい。実はそろそろ叙述トリックに気付くべきだったのだが、違和感を持ちながらも読み進めた。真相を見抜く材料は点在していた。うかつだった。 アリバイを崩したと思った後、その犯人と思われる一人遠賀野が交通事故で死ぬ。じゃあ、柳沢がやはり真犯人なのか。それにしてはおかしい個所もある。そして、「第4章真相」へとなだれ込む。とびらのページにこう書いてある。 「あなたは、このあと待ち受ける意外な結末の予想がつきますか。ここで一度本を閉じて、結末を予想してみてください」。 おっと、読者への挑戦かい。予想を試みるが無理だ。まったく予想がつかない。あるいはさらに思いがけない犯人が現れるのだろうか。まさか探偵役の2人のどちらかが犯人か。そんなことより、早く読んで結末を知りたい。意外な結末とは何なのだ。いったい犯人は誰なのだ。 すべてが明かされた。少し怒りたくもなった。無理やり、強引にそう来るのか。最近の本の中にも似たようなのがあったな。綾辻行人の館シリーズにも伊坂幸太郎にも、それから乾くるみの作品にも。トリックのキーワードは時間(ネタバレ)。 40年前、まだ叙述トリックという言葉もなかったころの作品である。今でこそ、いろんな叙述トリックが出回っているが、当時は衝撃的だったのだろう。それがなぜ今書店一押しの平積み本にされているのだろう。とりあえず、もう1冊の方も読んでみよう。 |
Hama'sPageのトップへ My Favorite Mysteriesのトップへ