| 2014年3月4日(火) 「狼と兎のゲーム」(我孫子武丸・著)を読む |
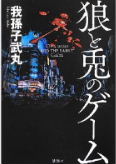 母親は疾走、茂雄(父親)はハンパじゃない暴力オヤジ、まさにカイブツだ。なのになぜか交番に勤める警察官だ。この設定無理じゃない?息子の担任、アンナ先生を暴力で凌辱し、子どもたちを助けた韓国パブのホステスにも瀕死の重傷を負わせる。推測だが疾走したとされる妻も殺したらしい。 母親は疾走、茂雄(父親)はハンパじゃない暴力オヤジ、まさにカイブツだ。なのになぜか交番に勤める警察官だ。この設定無理じゃない?息子の担任、アンナ先生を暴力で凌辱し、子どもたちを助けた韓国パブのホステスにも瀕死の重傷を負わせる。推測だが疾走したとされる妻も殺したらしい。2人の息子の名前は心澄望(こすも)と甲斐亜(がいあ)。みごとなキラキラネームだ。夏休みのある日、心澄望と友人の智樹は、庭で穴を掘る茂雄の傍らに甲斐亜の死体があることを目撃する。なぜか警察に告げず(実はこれは伏線だった)2人は逃げる。甲斐亜を殺したのは父親だと思い(実はそうではなかった)、次は自分たちが殺されるとの恐怖心からだ。 どこに逃げる?心澄望の母親が住んでいると思われる東京だ。ハガキの住所を頼りに、小学生2人が関東圏の街から新宿の大久保に向かう。暴力の権化と化したカイブツ茂雄が2人を追う。つまり、「狼(茂雄)と兎(小学生2人)のゲーム」なのだ。 2人の行方を追って、手がかりをつかもうと担任のアンナ先生宅を訪れる茂雄。アンナ先生は魅力的な独身の先生だが、警察官・茂雄にとっては欲望を満たす対象物でしかなかった。凌辱という最悪の展開。こんな男が警察官だとは。小学生が主人公だが、小学生にはこんな小説を読ませられない。 アンナ先生には2人の救出劇に加わってほしかった。あるいは茂雄に対する復讐を果たす、そんな展開を期待したが、それはなかった。まるで虫けらみたいに茂雄の餌食となるだけだった。 昔「逃亡者」という海外ドラマがあった。すんでの所で捕まらず逃走を繰り返す。あのテレビ番組を思い出した。ドキドキしながら読み進める。警察署に飛び込めよと言いたいが、2人の逃亡先に警察署は選択肢としてない。ドキドキ、ハラハラ、そしてイライラも。 そして2人はついに茂雄に追いつめられる。ここから、我孫子武丸、ミステリー作家の本領を発揮する。どんでん返しが待っているし、さらに智樹の証言で事態がひっくり返る。作者は読者の予想を思い切りひねくり回す。 救いのないストーリーである。どんな着地点を見出すのか。おっと、そうくるのか。ハッピーエンドではないが、少しは救われる。それにしても後味はいいとは言えない。こんな悪徳警察官がいるものか。DVや虐待に学校が気づかないはずがない。 |
| 2011年6月22日(水) 「眠り姫とバンパイア」(我孫子武丸・著)を読む ナルコレプシー、分かる? |
 授業中いつも寝てばかりいる生徒がいた。コツンと頭を小突かれ、一時目を覚ますがすぐにまた寝入る。 授業中いつも寝てばかりいる生徒がいた。コツンと頭を小突かれ、一時目を覚ますがすぐにまた寝入る。商談中、客の目の前で眠ってしまった会社員。成績が上がらずリストラにあったという。 会議中、上司が挨拶しているのに舟を漕いで大目玉をくらった同僚もいた。 デートで映画を見ていて、すっかり眠り込み、目が覚めたら相手はいなかったとか。 このように、睡魔に抗えない情けない人は、もしかしたらナルコレプシー(居眠り病)という睡眠障害かも知れない。昔はそんな病気があるとは知らなかった。だから居眠りをする生徒(もちろん大人も)は怠惰というレッテルを貼られ、本人も人知れず自己嫌悪に陥っていたかも知れない。 ちなみに「朝起きが悪く、午前中調子が悪い」子どももいる。起きてこないから遅刻したり学校を休んだり、そして徐々に不登校となる。周りはその子をやはり怠惰な子どもと見る。しかし、それもまた病気かも知れない。午前中起きて来れない病気、起立性障害という。そんな知識がまったくない担任教師は、自宅に押しかけ眠っている生徒の布団をはいで学校に連れてきたという。それで症状が良くなるはずがない。 昔はナルコレプシーも起立性障害もまったく知らなかった。最近は徐々に知られるようになってきたが、それでもまだまだマイナーな病気で、病気と思われず誤解されるケースも多いだろう。もちろん医者の診断を経て薬で症状が改善される病気だというが、そんなナルコレプシーを知らない大人に読んでもらいたいのがこのミステリーだ。 この本の主人公10歳の優希がまさにナルコレプシー。クラスでは眠り姫とあだ名が付いている。 寝ているのか起きているのか、優希はクリスマスイブの夜、3年前に交通事故で亡くなった父親に会う。帽子、マスク、マフラー、コート姿で顔は良く見えない。 同じ時期にその地域にバンパイアのような不審者がいるという噂が広まる。果たして死んだ父親がバンパイアとなって娘の前に現れているのか。父親が密室から消えた謎、鏡に映らない謎、本当に父親は死んでいるのか、バンパイアなのか。家庭教師の大学院生、荻野歩実がその謎に挑戦する。 「講談社ミステリーランド」のために我孫子が書き下ろした作品。父親の正体が気になるが、ラストは、な〜んだというレベル。ちょっと拍子抜けする。 |
| 2011年1月12日(水) 「弥勒の掌」(我孫子武丸・著)を読む |
 これも叙述トリック。作者が読者をだましにかかるのが叙述トリックだが、まじめな読者は怒りだすかも知れない。例えば、ある登場人物が男のように記述されていながら実は女だったり、殺人の時が現代のように思わせておいて実は10年前だったり。作者の仕掛けは時として読者に対してアンフェアと思われる場合も多い。 これも叙述トリック。作者が読者をだましにかかるのが叙述トリックだが、まじめな読者は怒りだすかも知れない。例えば、ある登場人物が男のように記述されていながら実は女だったり、殺人の時が現代のように思わせておいて実は10年前だったり。作者の仕掛けは時として読者に対してアンフェアと思われる場合も多い。本書もフェアではない。三人称記述なら客観記述であるべきなのに、読者の推理に必要な事実をあえて記載していない。あの後○△が殺人を犯していた。そんなバカな。書いていないじゃないか。ラストである人物によりあの後の殺人が暴かれる。読者はそうだったのかと驚くが、やっぱりフェアではない。 ある重要人物の名前も、だまされる方が悪いと言われるかも知れないが、名前だと思っていたら名字だった。名字だと思って読んでいたら名前だった。そんなミスディレクションもある。確かに名前とも取れる名字だった。 失踪した妻を追う高校教師と、妻を殺された刑事の章が交互に記述される構成だった。徐々に両者に関わってくるのが新興宗教、「救いの御手」。なぜ妻が失踪し、もう一人は殺されたのか。新興宗教信者が2人の妻を殺したり隠匿しているのか。最終章の前までとても面白く読めた。 しかしラストの収め方がまずい。予想もつかなかった収束ではあるが、ご都合主義ではないか。満足感が足りない。後味も悪い。結局あの新興宗教は問題なかったということか。1000円ほどの弥勒像を30万円で買わせる宗教団体が正義の味方であり、結局弥勒が探偵役も務めるのか。裁判にかけられそう時になると穏便に解決される、その理由も明かされなかったと思う。取ってつけたような収束であり、無理やり感が否めない。だったら、ラストでもう一度大どんでん返しが欲しかった。 |
| 2009年11月26日(木) 推理小説、「探偵映画」(我孫子武丸・著)を読む |
| 映画界の鬼才・大柳登志蔵が映画の撮影中に謎の失踪をとげた。純粋に謎解きを楽しむ映画「探偵映画」の解決編のみが未撮影だ。結末がどうなるのか、犯人は誰かなど、監督自身しか知らない。残されたスタッフは、撮影済みのシーンからスクリーン上の犯人を推理していく。 ミステリー好きで映画好きには1冊で2度も3度もおいしい推理小説だ。古代史や医学、人体解剖学の薀蓄をぶちまけられるより、映画の薀蓄ならいくらでも大歓迎だ。さらに映画の中の犯人当て、実際の監督の逃亡劇の真相と、1冊の中にミステリーが2つもあるようで、なんともお得な小説だった。 序盤で、叙述トリックについて詳しく説明される。叙述トリックとは作者が読者にしかけるトリック(犯人が仕掛けるトリックではない)。たとえばラストに判明する、主人公が実は女だったなど。これは小説だからこそ可能で映像では不可能だ(叙述トリックでは折原一や歌野晶午が有名である)。 しかし映像でも叙述トリックは可能で、たとえば「マッドマックス2」がそうだという。「マッドマックス2」は僕も見た映画だが、あれのどこが叙述トリックだったのだろう。ある人物があの映画の内容を語り、ラストに誰がこの映画を語っているのかが明らかになる、ということらしい。その他叙述トリックの映画がこれでもかというほど紹介される。「サン・ロレンツォの夜」、「悲愁」etc 主人公の立原と照明助手、水野晴之(映画評論家・水野晴郎みたいな名前だ)の映画薀蓄クイズも楽しい。「北北西に進路を取れ」と「新サイコ」のラストの共通点を知ってるか。あれには性的な意味が込められているのだ。「北北西〜」の原題は「North by Northwest」だが、これはいったい何のこと? さて、映画の登場人物たちは全員が意外な犯人役になりたい。それぞれが動機と殺人方法を説明する。かなり強引な人間もいるが、その後の役者人生のためにこの映画で一番目立つ犯人役をやりたいのだ。果たして監督は彼らの誰を犯人としてこの映画を作ろうとしたのか。そして監督の失踪の理由とは? ラストに意外な人物関係も分かるし、監督の失踪との関係も判明するが、結局、このミステリーでは誰も殺されない。殺されるのは映画の中だけで、劇中劇の謎解きの方が面白い。安孫子武丸らしい文体で読みやすいし、人物のキャラも軽く、楽しく読める変化球ミステリーだった。 |
| 2008年6月10日(火) 「メビウスの殺人」(我孫子武丸・著)を読む 数字の謎は「相棒」がぱくった? |
| 先日読んだ同著者による「8の殺人」。8の字型の屋敷で起こる不可解な殺人事件を速水3兄妹が解決する、おふざけのようでもある本格物だった。我孫子武丸はこの処女作の後、「0の殺人」、そして「メビウスの殺人」と続く、速水3兄妹3シリーズを発表する。 つまり、「メビウスの殺人」は速水3兄妹シリーズの最終作である。主な冒頭の登場人物欄で、「椎名俊夫…学生。連続殺人犯」とある。と言うことは、倒叙モノ(犯人を最初に明示し、犯人の側から物語を書くミステリー)か。倒叙ミステリーも、犯人は誰かを推理する楽しみはないが、それでもそれはそれで楽しい推理小説だ。 しかし、「メビウスの殺人」は倒叙モノともちょっと違う。どうやら犯人は2人いるらしい。パソコン通信(略してパソ通、懐かしい言葉だ)で連絡を取り合い、殺人現場になにやら暗号めいた数字(2−3など)を残す。事件は連続無差別殺人事件へと発展する。さらになんと被害者の名前が尻取りになっている。この規則性が公表されると、人々はパニックに陥る。次は「あ」で始まる名前の人が犠牲者になるであろう、などと。 パソコン通信、モデム、フロッピーディスク保存など、時代を感じさせる小道具だが、内容は現在のインターネット犯罪で十分通用する面白い作品に仕上がっている。ただ、もう1人の犯人は普通に読んでいても正体がばれるだろう。このトリックは少し興ざめである。あまり使ってはならないトリックではないか。さらに、2−1など犯行現場に残された数字もたいした意味を持たないゲームに関するものだった。拍子抜けである。 この数字の秘密が先日観た「相棒−劇場版−」でも使われていた。こちらは2−e、6−gなどアルファベットが組み合わされるが、「メビウスの帯」からのパクリかと、映画館でもやはり興ざめ。 相変わらず(と言っても読んだのは2作目だ)、速水3兄妹と木下刑事のドタバタぶり(スラプスティックというのだそうだ)ぶりが笑わせる。鈍器で殴り殺したり絞殺する場面が多いが、暗くならない。殺人事件の悲劇性は書かない。犯人の母親の苦悩も書かない。連続殺人をゲームのように実行し、作者はゲーム感覚で読者に挑戦する。 メビウスの帯とは1回転ひねって作った表も裏もない輪である。ということは・・・。む、む、題名が犯人のヒントとなっている。 |
| 2008年5月22日(木) 「8の殺人」(我孫子武丸・著)を読む トリックは分かりやすい |
| 「八の殺人」ではダメ、「8の殺人」でなければならない。文字通り8の形をした”8の字屋敷”で殺人は起こる。男は誰も入れるはずのない、つまり密室から放たれたボウガンで殺され、女は閉ざされたドア、つまりこれも密室のドアの内側に磔(ハリツケ)にされた。2つの殺人が密室に関わる、いわゆる密室殺人だ。ラストで探偵役の速水慎二が講釈をたれる密室談義が楽しい。関係者を一同に集めて「犯人はあなたです」、そして一応、どんでん返しもある。 トリックに繋がる伏線を、作者はサービス過剰かと思われるほど惜しげもなく散りばめる。左右対称の8の字屋敷は点対称でもある。ミスディレクションと思しき、犯人は左利き説(誰が信用する?)、遺体を数メートル引きずった跡、美津子の部屋にあったある物、常夜灯の電球交換、カーテンなど、それほど深く読み込まなくてもトリックは分かりそうだ。さすがの僕も(珍しく!)分かったぞ。 先日読んだ講談社ノベルズ「長い家の殺人」は歌野晶午のデビュー作。今回読んだ「8の殺人」は我孫子武丸のデビュー作だ。どちらも島田荘司が世に送り出したという本格派の新人(89年当時)推理小説家。巻末にある島田荘司の「本格ミステリー宣言」は読み応えある。さすが、本格派の巨匠。しかし、歌野晶午の時もそうだったが、我孫子武丸を褒め過ぎという批判もあるとか。 これが我孫子の筆致なのだろうか、あるいはこのシリーズ(0の殺人、メビウスの殺人など)に限った雰囲気なのだろうか、本格モノなのに笑えるユーモア小説。恭三と木下の凸凹警官コンビや3兄妹のおとぼけ、脳天気さ。事件を解決しなければならない刑事が犯人かも知れない女性(口がきけない)に恋心を抱いてどうする?いやはや、ドタバタやロマンスでも味付けされる異色の、あるいはおちゃらけの本格派。それでもツボは押さえた本格ミステリー。本格ミステリー入門の1冊としてもお薦めだろう。 |
Hama'sPageのトップへ My Favorite Mysteriesのトップへ